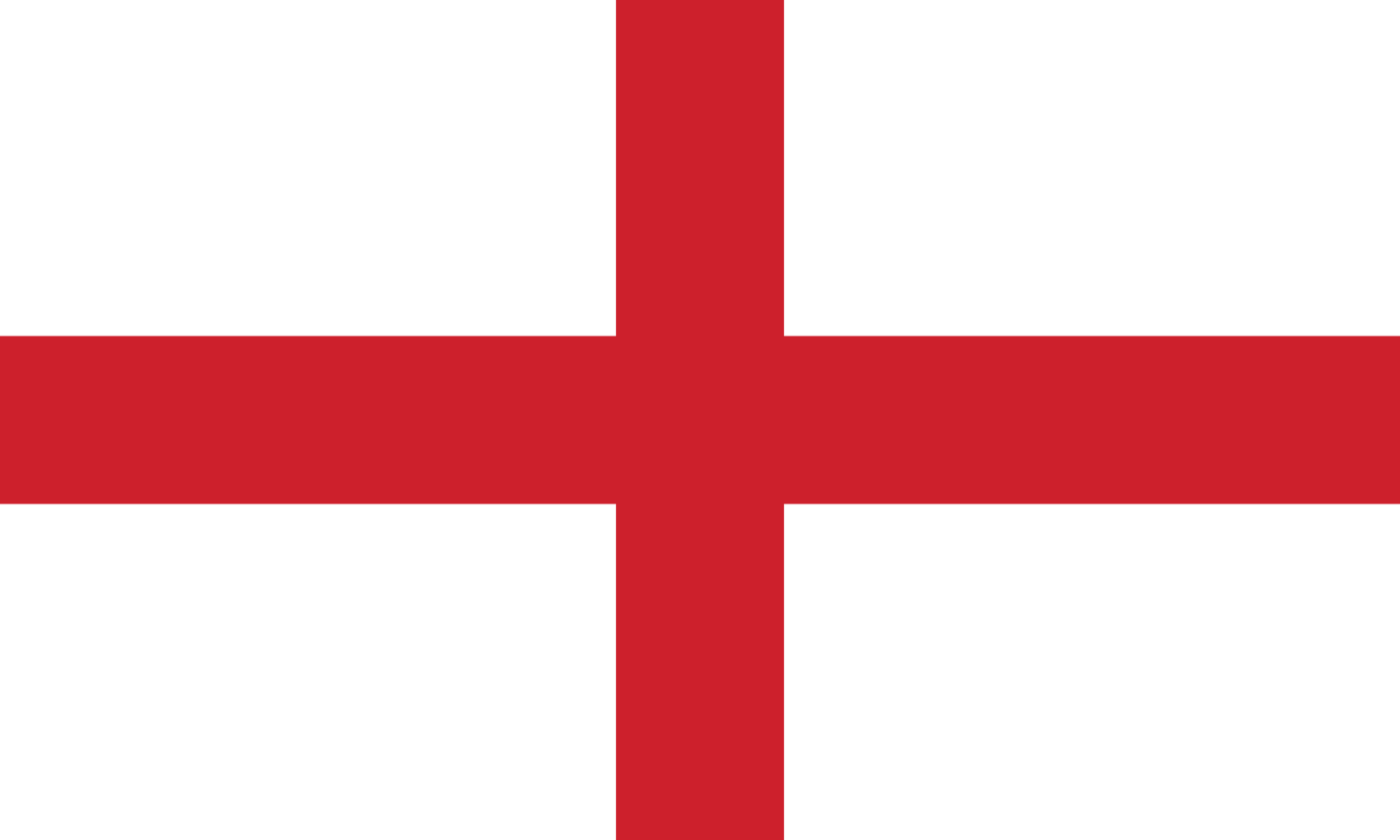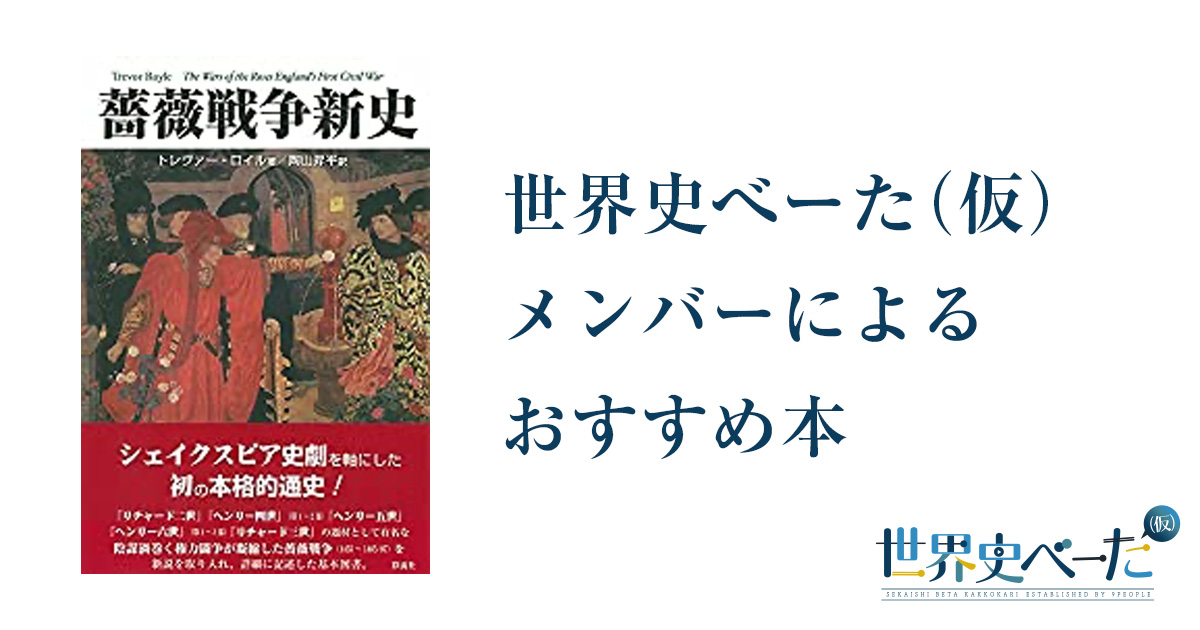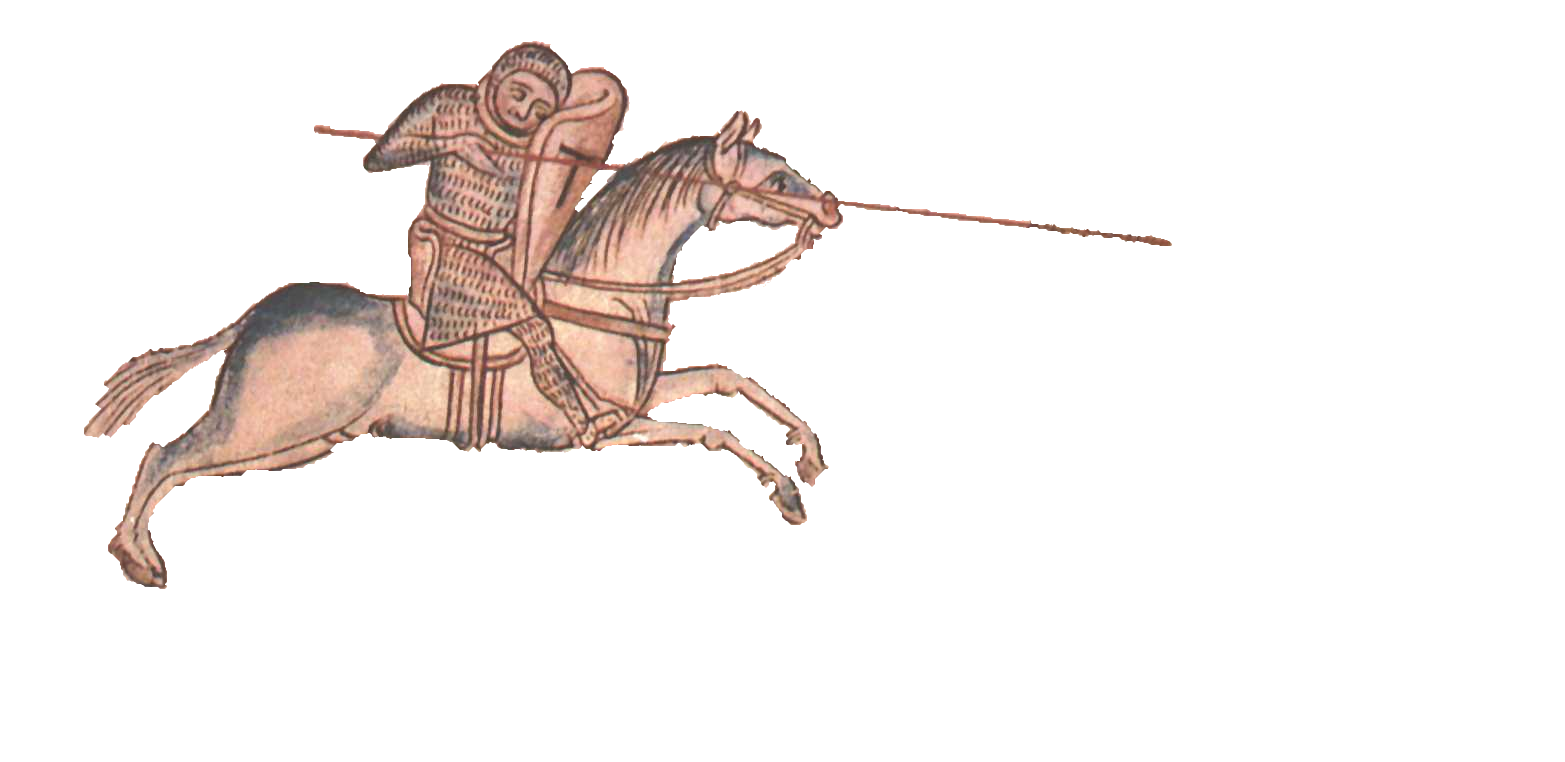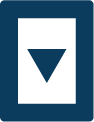まず最初に断っておくと中世に国民体育大会はありませんでした。国体は国のありようと言うことです。考え方としては戦前でよく言われてたのような国体に近いのですが、イングランドでは文字通り「体」のように考えられていたようです。国王を頭として軍隊や貴族、忠誠、臣民、税、宮廷、修道院、さまざまな構成物がまるで人体のように相互に支え合って国体が動くというわけですね。 さてこうした国体は中世を通じて同じであったわけではありません。ローマ帝国崩壊後の異民族の侵入の頃の状況はよくわかっていないのですが、この時期の族長の周囲が国体のもとになり、次第に膨れ上がっていったのです。 まず族長の周囲には長老だとか人望のある人だとかが集まってあーするべきだとかこーするべきだとか意見を聞くための集団がいます。ノーサンバランド王のエドウィンはキリスト教に改宗したヘプターキー時代の人物ですが、改宗に当たって重臣たちを説得しているシーンが年代記に残されています。こうした重臣たちの集まりは後にウィタンと呼ばれていたそうです。イングランド議会はHPでこのウィタンがルーツの一つであると説明していますが、中世に三権分立などと言う概念があるわけがなく、最初の実態としては全ての権限が混然一体となった偉い人たちの会議でしょう。もっとイメージしやすく言うなら会社の重役会議だとかヤクザの組長の舎弟たちなわけです。 組長=王 舎弟=貴族 子分=宮廷の使用人など 舎弟がいれば子分もいます。こんな風に書くと仁義なきイングランド史というタイトルが頭をよぎりますが、実際未発達で暴力に頼らざるを得ない社会だったので自然と似てくるものなのだと思います。子分の仕事は組長の身の回りの世話となるでしょう。今と違って家事労働は大変なこと、一人暮らしなんて修行者の域だったかもしれません。衣装を管理し、財産を管理し、食事の場をセッティングし、馬を世話し…いろんな仕事がありますね。こんなの家政婦の仕事で子分の仕事じゃないなんて思わないでください。今だって弟子が師匠の身の回りの世話をするような芸事があったりするでしょう。実際王のトイレの世話は貴族たちの間でも特に信頼の厚い人物にしか任されなかったのですから。 さて、子分たちの話に移りましょう。ヘプターキー時代も終わりが近づくと族長と言うか王の支配領域は広がります。市町村レベルから大きめの県レベルまで大きくなります。王は広い領土を旅しながら治めました。各地の諍いを解決するために、住民の忠誠を引きとどめておくために、反乱の芽が出ていないか確認するために。この移動に伴って王の衣装も財産も動くのです。と言うわけでチェンバレンが生まれました。チェンバレンは王の寝室に関連する仕事をしていたのですが、今でも寝室には重要なものが置かれることが多いように(ネットで元空き巣の証言を読んだところ、基本的にリビングか寝室には現金があるなどと言ってました)、重要な書類や財産の管理を任されました。しかし王たるものそういったものは山ほど抱えることになります。膨れ上がった貴重品をすべて寝室には置いておけません。そこでトレジャリが生まれます。トレジャリは宝物庫を管理する役職ですが、あまりにも多い財宝はウィンチェスターに定着しました。そしてこのウィンチェスターにある財産を適切に管理しているか調査をしたり、王の収入を把握するためにエクスチェッカー(財務府裁判所)が作られるのです。この辺りの歴史はまだ私の中では腑に落ちないし分からないことも多いので、立ち入った話はできませんが、どうもただの会計ではなくて裁判もしていたようなのです。ちなみに行政面についても多方面にわたって活躍したようです。イギリス史ではやたら不思議な裁判所がたくさん出てくる気がするのですが、そもそも三権を分立させていない状態だとすべては司法の下に属するらしいです。一方で金勘定して一方で会計をごまかした人物に罰を与え、しかも同じ会合で全く財政とは関係のない事務処理や裁判までついでにやっていたのかもしれません。学級会で掃除当番を決めていたら突然弾劾裁判が始まってしまうような…カオスな役所だったのでしょう。このあたり、名前に引きずられて組織の仕事を判断してはいけないなとよく思います。あと、コートの法廷に代わる様ないい訳はないのかと思いますね。 舎弟に話を移しましょう。組長は多くの舎弟を従えることになります。特にノルマンコンクエスト以降の重役会議はクーリア・レギスと呼ばれます。ここも会議で掟を決めているかと思えば裁判もしているところです。クーリア・レギスめちゃくちゃいろんな人が出席するようになったので、大会議と小会議に分かれました。小会議が様々な行政機関や専門裁判所として成長し、大会議は議会として国体の土台に変貌していきます。まるで胚が細胞分裂で一つの細胞から様々な臓器に変わっていく様子みたいですね。ちなみに小会議は枢密院を生み出し、枢密院は内閣を生み出しています。そう、そしてその内閣の下に教育省だとか運輸省だとか国防省があるんです。 ところでノルマン朝やアンジュー朝はフランスを本拠地とした勢力です。いくらイングランドの土地が豊かでも本拠地はフランスです。そのため、イングランド王はノルマンディーにいるのが基本でした。なのでイングランドの統治を担当したのはジャスティシアー(最高法官)と呼ばれた人です。このジャスティシアーがいた頃がちょうどクーリア・レギスの分裂が活発だったころでもあり、王の不在と言うのはイングランド独特の行政制度の発展に大きく寄与したと思われます。ジョン王がノルマンディーを失い、イングランド王の本拠地がイングランドになるとその発達した行政機構や裁判所が王を迎え入れることになりますが、そこで王と貴族の確執がマグナ・カルタを生み出し、議会が税の承認をする伝統が生まれました。 議会と言うのは今でこそ立法府ですが、中世においては課税の承認をする機関で、その代償として各地域の陳情を持ち込んでいたようです。上納金を納めるからには自分の組のいざこざや困りごとの面倒は見てほしいですからね。この陳情が時には権利の請願だとかウェストミンスター条項、改革勅令になるわけで、議会を強くしていきます。しかし議会は王を懲らしめたいわけではなく、やはりその権威に依存しましたので持ちつ持たれつ、議会の中にあって王は主権を有するなどと言うあいまいな国政論となるのです。このぼんやりした制度は王を体の一部とした、つまり王が単独では生きていけない状態を作り、国体と言う発想になったのかななどと思ったりもします。 イングランドの複雑な政治史の驚くべきところは、大きな切れ目なく現在まで続いていることです。私たちの暮らしを支える国のシステムは近代(この言葉のせいで18世紀以前の世界と必要以上に距離を感じますね。同じ体を持つ人々だというのにまるで違う生き物のようにさえ感じてしまいます)に突然生まれたものではなく、中世から脈々と受け継がれてきた、秘伝のたれのようなものです。私たちを取り巻くシステムは、暴力渦巻く民族移動の時代から、試行錯誤や改良を重ねて生まれてきたもの。この知恵はもちろん現代の制度を知ることでも得られるでしょうが、その神髄は歴史に触れることでより一層分かるのではと思って、ずっとイングランド史を続けています。たぶん。
Category: メスキィタ
薔薇戦争新史
シェイクスピア史劇を軸にした、わかりやすく本格的な初の通史! 英国初の内戦(1455-1485/87)であり、シェイクスピア史劇(『リチャード二世』『ヘンリー四世』(第1 ~ 2 部)『ヘンリー五世』『ヘンリー六世』(第1 ~ 3 部)『リチャード三世』)の題材としても知られる薔薇戦争を、史劇を足掛かりに、ワット・タイラーの乱、百年戦争、ジャンヌ・ダルクなど戦争期間以外の背景も丁寧にたどり、新説を取り入れながら詳細に記述した英国・欧州中世史・軍事史研究の基本図書。 【アマゾン書籍情報から引用】 おすすめ本です たぶんこれが一番詳しいと思います(日本語では)。 といって私は全部読んだわけではありませんが。やはり歴史をとことん調べるときには一次史料などにあたるのですが、何の事前知識もなく入るのは非常に大変です。読書はステップを踏んで進むものだと思っています。この本は2ステップぐらい踏んだ人が読むことをお勧めします。 本は薔薇戦争の始まる50年以上前までさかのぼって経緯を説明しています。そこまでさかのぼる必要があるほど薔薇戦争は経緯が複雑なものだからです。そもそもランカスター家はなぜ生まれたのか、そしてそこにはどんな問題があったのかを意識すると薔薇戦争は分かりやすくなるでしょう。 ところでプランタジネット朝以降のイングランド史は王に対して次々と有力者たちが行動をエスカレートさせた様子とそれに対し折り合いをつける様子を見ることができます。ヘンリー2世とリチャード1世の時代は王家で争いが起こり、ジョン王の時代には反乱者がマグナカルタを突き付け、ヘンリー3世の時代には反乱者が議会の元を生み出しました。エドワード1世は議会と協力し中世の名君となりましたが、エドワード2世は廃位されて息子が王位につきました。この時イングランドで初めて王が貴族に殺されるのですが、王朝の交代は起こりませんでした。そこから飛んでリチャード2世は子を持たず王朝交代が起こったのですが、このことが50年もたって百年戦争敗戦による諍いが起きたときに利用されたのです。 さて、薔薇戦争は結果として国王の廃位が30年で4回も起こる混乱を引き起こしました。この混乱後はテューダー朝の体制が出来上がるのですが、それも宗教問題で混乱が起こり、引き継がれたステュアート朝では財政問題と合わさって、ついに国王不在の政治体制が出現しました。 イングランドの長い歴史の中で薔薇戦争はどんな意味を持ったのか、そこも考えてみるのも面白いと思います。浅学の身の私ではまだまだ難しいことですが。 書籍情報 著者:トレヴァー・ロイル 翻訳者:陶山 昇平 編集者:– その他:– 出版社:彩流社 出版年:2014/7/24 ISBN-10:4779120322 ISBN-13:978-4779120329
ホッブズ編集後記
哲学系の動画はほとんど上げてきたことはなかったのですが「少しは勉強した方がいいだろう」と言うことで挑んでみました。もともと哲学に興味があったわけではないのですが、知識人と言われているような人はよく哲学用語などを使いますので、私もカッコつけたいという不純な動機で哲学をかじるようになった次第です。 さて、ホッブズ以前の時代と言うのはキリスト教が科学であり法律であり、教育でした。何か物事を考えるうえでは何かしら神にさかのぼることが当然のことだったわけです。なぜ王が国を支配できるのか、それは神に選ばれた存在だからです。そうした思想を背景に儀式などが進められているのは聖書に倣って即位時に油を塗られることなどからもわかるでしょう。しかし、宗教改革でキリスト教が分裂すると宗教と言うものが相対化されます、本来宗教は一つの正しいものがあってそれ以外はこの世界の説明に適さないものでした。宗教改革では様々な説明が生まれました。この世界に人が死後天国に行くにはどうすればいいのか、善行を積めばいいのか、神様があらかじめ決めているからどうしようもないのか。どれか一つが正しい説明であるならば、そして神が存在するならば、誤った方が消えてもよいと思うのですが、そうはならず、様々な見解が長年にわたって共存することになりました。私は浅学の身なのでこの辺りに限らず思想史についてはまだまだ読書不足ですが、このカオスの中で神を抜きにして世界の説明を試みる人が現れても不思議ではなかったのでしょう。ホッブズは王が国を支配する理屈において、神を抜きに語りました。ホッブズ自身は無神論者だとは言っていませんが、他人からは無神論者だといわれる程度には神と言うものを重視しする説明はしていなかったようです。 神を手放してしまったことについて、私はそこまで理性的な人間ではないので、実にもったいないことをしたなと思います。特に小学生の頃でしたが、自分は死んだらどうなるんだろうかと言うことを考えて恐怖を覚えたものです。脳機能が停止して夢すらも見ることが無くなった「私」はどこに行くのか、外部からの刺激が一切ない真っ暗闇の中永遠の時を過ごすのか、そもそも永遠の時を認識する「私」はいなくなっているのだろうか、でもいまキーボードをたたく「私」が途切れたとしてその先に何があるのか。死んだ人の体験談が聞きたいのですが、死んだのなら聞けるはずもなく、死ぬ時まで持っていく疑問なのだろうと思います。死んだら煉獄に行くやら、もう一度生まれ変わるやら、単純にそう信じて、信じ込んでおきたかったなと思う次第です。
よく使う素材について
メスキィタがよく使う素材サイトです。動画を作りたいという方がいらっしゃったら、参考になさってください。 音源 クラシック音楽へのおさそい~Blue Sky Label~ http://www.yung.jp/index.php 効果音ラボ https://soundeffect-lab.info/ wikimedia https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page DOVA-SYNDROME https://dova-s.jp/ 画像 いらすとや https://www.irasutoya.com/ wikimedia https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page 画像の切り抜きにはGIMP 2.10.6を使用していますが、PSDファイルの加工にはFireAlpaca64を使用しているため、今後変わる可能性はあります。 動画編集ソフトはAVIUTLで、音声合成ソフトはVOICELOIDのキャラクターを使用しています。AVIUTLには各種プラグインやスクリプトを導入しています。
メスキィタの生態
世界史の動画をたくさん作りたいと思っていましたが、イングランド史ばかり作って世界史をだいぶ忘れてしまった者です。特に興味があるのが名誉革命から南海泡沫事件までの間、このころの社会について勉強したいと思っています。が、横道それてばかりで薔薇戦争で泥沼にはまってしまいました。 今後はアイルランド史やスペイン史、アラブ史など手を広げていきたいのですが、いつになることやらわかりません。 ひとまず、イングランド史の動画に精進いたしますので、皆様、変わらぬご愛顧のほどどうぞよろしくお願いします。 ブログでは読んだ本、動画の素材、について語ろうと考えています。時間がありましたら、イングランド史の記事も執筆したいと思います。