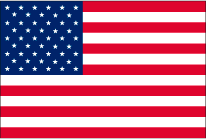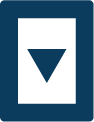お久しぶりです。せるヴぁんだです。今回のブログ担当ということで、「アメリカの裁判所」について徒然なるままに書き散らしたいと思います。 アメリカ「合衆国」というちょっと変わった国 The United States of America, 略してU.S.A。一昔前(?) に同タイトルの曲が流行りましたが、日本人としてよくよく考えてみれば、アメリカという国は奇妙な国家形態をしています。日本の場合、「国」と言えば日本国そのもの、その下の行政単位は県、市、区、群、町…というように刻まれていきます。(道州制万歳!) 一方のアメリカは、いわゆる連邦制国家なのです。2023年現在、全部で50州を抱える国ですが、この「州」という存在がいささか厄介なのです。おそらく、多くの人が州=県のようなイメージを持つのではないでしょうか。愛知県豊田市≒ミシガン州デトロイト市のように。 しかし、実際のところ、アメリカの各州は日本の都道府県よりもはるかに強い権限を持っています。なんたって「州の憲法」が作れてしまうのですから。(おまけに州兵という州知事直轄の軍事組織まで!そう、某Grand Theft Autoなゲームで手配度が最高になるとやってくる人たちですね)このため、アメリカという国には、連邦政府たる「アメリカ合衆国政府・議会・司法」と、小さな国家とも呼ぶべき、「州政府・議会・司法」が二重で存在しているのです。日本の地方自治体にもそれぞれ議会と行政は存在し、条例も制定できますが、さすがに憲法や法律(※1)は作れません。国の唯一の立法機関は国会のみと憲法で定められています。(第41条) ※1…多数ある「法」の中でも国会で制定された法を特に「法律」と呼びます。 一番の違いは「裁判所」の構造かも アメリカと日本は「三権分立」型の構造をしています。議会(立法)・行政・司法の三すくみですね。そのなかで、議会と行政については、上に見た通り、権限の強弱があるとはいえ、ある程度は似通っています。しかし、司法たる裁判所はまったく違う構造をとっています(なぜでしょうね?)この違いの原因を探るところまではパワーがないのですが(すみません。。。)ここでは組織構造の違いを簡単に紹介しようと思います。 1.日本 日本の場合、司法制度の頂点たる最高裁判所が1つあり、日本を八つの管区に分けて高等裁判所が設置されています。その下に第一審となる地方裁判所・簡易裁判所・家庭裁判所がたくさん存在することになります。このように、最高裁をトップとする単一ピラミッド構造が日本型司法制度ですね。 2.アメリカ アメリカはというと、裁判所も「連邦政府」と「州政府」の2つのピラミッド構造を取ります。アメリカの統治システムは原則として州政府が責任を負い、州政府ではできないことや特に必要とされる場合に、連邦政府に権限があるようになっています。たとえば、合衆国憲法の解釈・適用に関する問題は、州の裁判所ではなく連邦裁判所が審理する権限(管轄権)を持っています。このように、連邦裁判所が管轄権を持つのか・連邦と州いずれの裁判所にも管轄権があるのかなど、個々の訴訟問題の性質によって、どこで裁判するのかが決まります。連邦と州を比べると、連邦の方が力があり、上下関係があるようにも思えますが、州の裁判所システムが連邦の裁判所システムに従属しているようなことはありません。あくまでも「異なる別の裁判所システム」としてそれぞれ独立しており、管轄権の競合があった場合にのみ、個別に調整されています。(たいていは連邦法が優先します) A)州裁判所システム アメリカで提起される訴訟のほぼすべては、州裁判所へと持ち込まれます。州の裁判所システムは各州によって様々であり、特に統一されているわけではありません。基本的には州地方裁判所(District Court/Trial Court)・州控訴裁判所(Court of Appeals/Appellate Court)・州最高裁判所(Supreme Court)の三審制ですが、州によっては控訴裁判所がなく、第一審と最高裁判所の二審制を採る州も存在します。(デラウェア州、サウスダコタ州、ワシントンD.C.など) さらに、州によって憲法や法律の内容、蓄えられた経験(先例となる判例法)も違うため、同一の訴訟を別々の州で提起すると、必ずしも同じ結論や量刑にならない可能性もあります。有名な話では、国際的な企業が準拠法と管轄裁判所(※2)を選ぶ際、アメリカではニューヨーク州とデラウェア州が多いそうです。(デラウェア州なんて何もないのに!)これは、2州が企業紛争に関する豊富な先例を蓄えているからと言われています。 ※2…事件・紛争が起きた時、どの国・州の法律に基づいてどこの裁判所で審理するかということ。 また、アメリカ裁判所制度の最大の特徴と言ってよいのが、「巡回裁判所(Circuit Court)」の存在です。巡回裁判所はその名の通り、管轄する地区をぐるぐると巡回して移動式の裁判をしていたのです。残念ながら今はもう存在しませんが、馬に簡易的な審理台を引かせて、判事が裁判をして回っていたそうですよ。(当時は上等なクッションもなかったので、長時間の移動と審理で判事のお尻が破壊されたとの説も) (画像引用:HJ Erasmus, Circuit courts in the Cape Colony during the nineteenth century: hazards and achievements,Fundamina… Continue reading アメリカの裁判所について
Author: せるヴぁんだ
- せるばんだ
- 近現代史、国際公法
- 庶務(?) 法学×史学のテーマで何かやってみたい
- 【国連解説】人類は世界平和を目指した〜国際連合の光と影〜第1回 国連成立への道のり
- 時勢柄、国連の注目度が上がっていたので、これ幸いと作成しました。世界機構成立の裏には、こんな歴史があったのです...。
- byゆはる|【高校政経】結月ゆかりの高校政経『冷戦の成立』
- 視聴者さんの中には、リアルで体験していた世代の方がいるかも…?歴史の教訓を手短に、されどもしっかりと教えてもらえます。
条約ができるまで
こんにちは。せるヴぁんだです。 今週のブログ担当、略してブロ担となりました。 皆さんは『条約』という単語をご存じですか? 世界には数えきれないくらいの条約が存在しています。 日本に関係する有名な条約だと、日米安保条約・ワシントン海軍軍縮条約などがありますね。(社会科の授業で聞いたことあるはず!) 時代を遡れば、いわゆる不平等条約と言われた日米修好通商条約なんかもあります。 たくさんある条約の種類 実は、『条約』と名がついているものだけが条約ではありません。タイトルの最後に必ずその文言を付けて『〇〇条約』とする必要はなく、名称は何でもよいのです。 条約と名がついていないからと言って、条約でないということにはなりません。 国際連合憲章 国際連盟規約 国際司法裁判所規程 いずれも『条約』という文言は入っていませんが、立派な条約なのです。 条約ができるまで 条約案の作成 まずは条約案を作らないといけません。 たくさんの国が加盟国となるような条約(多数国間条約)の場合、その成立にはそれなりの期間を必要とします。 例えば、国際連合が旗振り役となっている条約の場合、最初から国連の全加盟国が条約の作成に関わるというよりも、一部の国が作業部会といった委員会を立ち上げて条約の骨子を作成することのほうが多いように感じます。 失礼ですが、全権委任状はお持ちでない? 各国は『全権代表』と呼ばれる代表者を自国から派遣し、条約交渉に関わるプロセスの責任者とします。 昔は、全権委任状という書状を提示しなければ、全権代表であると認めらませんでした。 明治時代に岩倉使節団がヨーロッパへ条約改正交渉に赴いた際、全権委任状がなかったため改正交渉に参加させてもらえず、大久保利通と伊藤博文が慌てて日本まで取りに帰ってきたというエピソードが有名です。 条約案がまとまったら 出来上がった条約案は、条約作成会議の全出席国の間で採決にかけられます。 要は、あなたの国はこの条約内容に賛成ですか?反対ですか?という訳です。 原則は全出席国の同意がなければ、条約として採択されません。けれども、非常に多くの国が参加している場合、全会一致が難しいことも多くあります。 そのため、出席国の2/3以上の賛成があれば成立する場合もあったりします。 そうして賛成多数/全会一致で条約内容が認められると、晴れて採択となり、各国代表の署名によって内容が確定します。 署名したら終わり?もう帰っていい? 署名行為には「条約の内容を確定させる」という効果があります。しかし、条約が正式に『法的文書』として拘束力を持つには発効要件を満たす必要があります。 例えば10か国の署名が必要だとか、アメリカを含む20か国の批准が必要、といった具合ですね。 前者では、10か国が署名されすれば、条約は法的拘束力を持ちます(発効)。ところが、発効要件が後者のような場合、さらに批准という手続きを踏まねばならず、署名の段階では、極論『紙切れ』状態にすぎないのです。 さぁ閣下、これに批准にしてくださいね 批准とは、『国家として正式に条約に従う意思を表明する』ことと言われます。重要な条約のほとんどは、署名だけではなく批准手続きを要求しています。それはなぜでしょうか。 第一に、全権代表(署名をした人=国連大使等)が、その国の本来の条約締結権を持っている人(国家元首等)の意思に反していないか、与えられた権限を越えて署名していないか、ということを確認するためです。 第二に、条約締結権者に「やっぱりや~めた!」の機会を与えるためです。最初見たときはイイと思ってGOサインを出しちゃったけど、改めて考えてみるとダメだこれ!なんてことがあるかもしれません。署名から批准に至るまでに、もう一度熟考してくださいね、という意味も込められているのです。 第三に、民主的手続きのためです。言い換えれば、議会において本当に結んでよいか判断するためです。自衛隊の文民統制と同じような考え方で、条約の締結にも民主的な統制をはたらかせるべき、というものです。 日本国憲法では、条約の締結は内閣の仕事です。したがって、原則として議会は条約締結の手続きに関与しません。しかし、それでは条約の民主的な統制が効かず、内閣が好き勝手に条約を結びまくることができてしまいます。 そこで、次の3つの性格のいずれかに当てはまる条約については、締結(批准等)に際して国会の承認が必要な条約として国会に提出しなければならないとしています。 法律事項を含むもの 財政事項を含むもの 政治的に重要で、批准が発効要件となっているもの この考え方は、1974年当時、外務大臣だった大平正芳氏の答弁に基づくものであるため、『大平三原則』と呼ばれています。 批准しましたことをご報告申し上げます 最後に、批准した旨を寄託国と呼ばれる国に通知します。条約の発起国だったり、大きな国だったり様々です。国連事務総長が寄託者になることもあります。… Continue reading 条約ができるまで
編集後記(11月5日公開 さとうささらの憲法解説)
お久しぶりです。今日のブログはタイトルの通り、編集後記です。 さて、先日の動画はお楽しみいただけたでしょうか? 国際法をメインに取り扱っている身でありながら、趣向を変えて憲法学にチャレンジしてみました。動画ではお伝えしきれなかったことを書いていきたいと思います。 法学×歴史学? 動画でも述べている通り、「憲法」は義務教育で唯一習う法かと思います。 あれは今から三万六千、いや一万六千年前だったかもしれません。私が小学生だった頃は、憲法前文を全文丸暗記しようね、などと言われ、覚えさせられた記憶があります。 当時はただの難しい長文でしたが、動画で触れた通り、憲法の立憲的意味があるからこそ、あそこまで重要視されるんですね。 これはまさに、人類が長い歴史の中で「権力に好き勝手させたら回りまわって国民が苦しむ」という事に気づいてしまい、さぁどうしようか?と頭をひねった結果なのでしょう。 そういう意味では、法学は歴史学と非常に密接な関係があるのではないでしょうか? 実際、著名な法が制定される前には、必ず何かしらの歴史的事件があるものです。 先日、SNSでこんな投稿を見た(気がします)。 『ロシアによるウクライナ侵攻で、国際法を受講する大学生が増えている。一方で、国際法はロシアの侵攻を防げなかったのだから無意味だ。国際政治学の方がよっぽど実用的だ』 まぁ、その通りかもしれませんが、このままでは国際法に限らず、法学全体が少し可哀そうなので補足をしておきます。 法学とは、『過去を省み、未来を見据える』学問と言えると思います。(※個人の感想です) 法を考えるときは、まず過去を振り返ります。「過去、こんなに凄惨な事件があったよ」「なんでだろうね」と。 そして、未来に視座を移し、「将来二度と起こさないためにはどうしようか?」と、う~んう~んと悩みぬく訳ですね。 そんな感じで、法を考える時は、その背景となった歴史上の出来事も関連してるんだよ~と思ってもらえれば、法学or歴史学のお勉強がもっと楽しくなるかもしれません。 憲法といえば改憲云々の議論は避けて通れませんが、改憲を考える時は、某条がどうのこうのだけに囚われず、動画で述べた「憲法の基本的な考え方」を是非とも思い出して頂ければ。 哲学者ってすごいよ 自然法思想に触れる際、避けて通れないのがT・ホッブズ、J・ロック、J・J・ルソーの御三方です。 他にも、法学に影響を与えた思想家としては、私の前々回動画で取り上げたグロティウス、ベンサム、JS・ミルなどがいらっしゃいます。 私は哲学分野はさっぱりなので、動画を作るにあたって資料を読むんですが、まぁ~すごいですね。 彼らの考えはなんかもう「私じゃ完全に理解するの無理だな~」となるくらい壮大です。 これを研究する哲学科って本当にすごいですね。(哲学科の先生に大抵ぶっ飛んでる人が多いのはひみつ) 人の思想を追いかけるのには、根気が要ります笑 要約ノートなんかがあればすごく便利なんですが・・・。 話は変わりますが、後年、私の動画を発見した哲学者が私の思想を研究対象にしないとも限りません。 そんなときに「このせるヴぁんだとかいうやつは何を考えて動画を作っていたんだ?」と貴重な時間を割いて頂くもの恐縮なので、ここに答えを書いておきます。 ささらちゃんもかわいいじゃん 編集もっと楽ちんにならへんかな~ 大学図書館に住みたい!24時間空いていて欲しい! 無料でコピーできませんか! 洋書を自動で日本語化してほしい(翻訳メガネ的なの欲しい) 以上です。ちなみに、今回ささらちゃんを起用したのは、仕事で全六花航空を利用したためです。 さて、ほぼ駄文でしたが、憲法解説「も」続くとおもいますので、また次回~。(シリーズものをやりすぎなんだよ)
アメリカ大統領選挙のしくみ(1)
みなさんこんにちは。せるヴぁんだです。 今日は7月5日。日付変更線を跨いで地図の右に目をやると、自由と民主主義の超大国が独立を果たした日(7月4日)ですね。 今頃盛大に独立記念日を祝っていることでしょう。 さてさて、今回のブログでは、アメリカの象徴ともいえる大統領の選挙について簡単に戯言を並べたいと思います。なんたって次の大統領選挙まで854日しかありませんから! 大統領になりたいやつ、この指と~まれ! という感じで、まずは大統領選挙に立候補する人々が集まらないと始まりません。 しかし、誰でも立候補できるという訳ではなくて、以下の3つの条件を満たす必要があります。 ① 生まれながらにして合衆国国民であること ② 35歳以上 ③ 14年以上アメリカに居住していること (合衆国憲法第2条1節5項) 何とも厳しいですね。日本人が大統領選挙に立候補したり、大統領になるために国籍を捨てて海を渡ったところで、人生もう一回やり直していただかないと大統領にはなれません。国籍の捨て損になってしまいますから、おとなしく日本のてっぺんを目指しましょう。 まずは予備選挙をしていただきます 私なら大統領になんてぜ~~ったいになりたくないですが(責任重すぎるもん)、現実には多くの立候補者がいます。けれども、悲しいことに大統領(+副大統領)のイスは1つしかないので、お集りの皆さんには椅子取りゲームをしていただかなくてはなりません。 このイス取りゲームは、予備選挙、あるいは党員集会という形式で実施され、勝った1名(正副大統領を合わせると2名)が公認候補としてイスに座ることができます。公認候補になるには、後に行われる全国党大会に出席した代議員の過半数に支持される必要があります。そのため、予備選挙によって候補者が代議員(イスのパーツ)を取り合う、といった構造になっています。 そうして、最も多くの代議員を確保した候補が晴れて「イス」を完成させ、公認候補となることができます。正式に公認候補となるのは全国党大会ですが、予備選挙の結果を見れば、大抵は公認候補になる(であろう)人が分かってしまいますがね(笑) 予備選挙?それとも党員集会? 予備選挙/党員集会のどちらの形式で椅子取りゲームを実施するのかは、その時の気分…ではなく、州法で決まっていて、2022年現在ほとんどの州が予備選挙を選択しています。 伝統的にアイオワ州の党員集会が一番最初(1月~2月)に開催されて、その後すぐにニューハンプシャー州が予備選挙を実施します。大統領選挙はこの2州から始まるのです。多くの州で予備選挙が実施される日があり、これを「スーパーチューズデー(なんかすごい火曜日)」といいます。 全国党大会「俺が!私が!公認候補!応援ヨロシクゥ!」 予備選挙が終わると、だいたいの州で公認候補となる2名(正副大統領1名ずつ)が判明します。 2020年の選挙では、民主党公認候補…ジョー・バイデン、カマラ・ハリス(副)/共和党公認候補…ドナルド・トランプ、マイク・ペンス(副)となっていました。 彼らは全国党大会でそれぞれ正式に党の公認候補となり、所属政党の全面的なバックアップを受けてタイマン勝負に挑むことになります。ここからいよいよ、本選挙の開幕です!
はじめまして
せるヴぁんだに関するブログ 第1条 目的 本ブログ記事の目的は、次のとおりである。 せるヴぁんだについて理解すること。そのために簡単な自己紹介を行う。 第2条 せるヴぁんだの定義 せるヴぁんだとは、主としてニコニコ動画において国際法学に関する解説動画の投稿行為を行っている者である。 せるヴぁんだとは、ラテン語の法格言”Pacta Sunt Servanda”-合意は拘束する-からとられたものである。 第3条 過去の投稿動画 代表的なものとして、紲星あかりの3分即決!国際法廷!シリーズなど。 他に、単発モノがニコニコ動画に寄託されている。 3分の題名は、時間概念としての3分に何ら影響を及ぼすものではない。 第4条 今後の方針 国際法全体の解説動画の投稿を試みることに努めなければならない。 前項に並行して、既存シリーズの拡充に努めなければならない。 世界史ベーた(仮)を盛り上げられるように、積極的に貢献するよう努めなければならない。 第5条 コメント このブログは、日本語を正文とし、世界史ベーた(仮)公式に寄託しておく。 というわけで、よろしくお願いいたします。 附則 リンク 3分即決!国際法廷「コルフ海峡事件」 STATE WARS 拒否権の覚醒



.png)