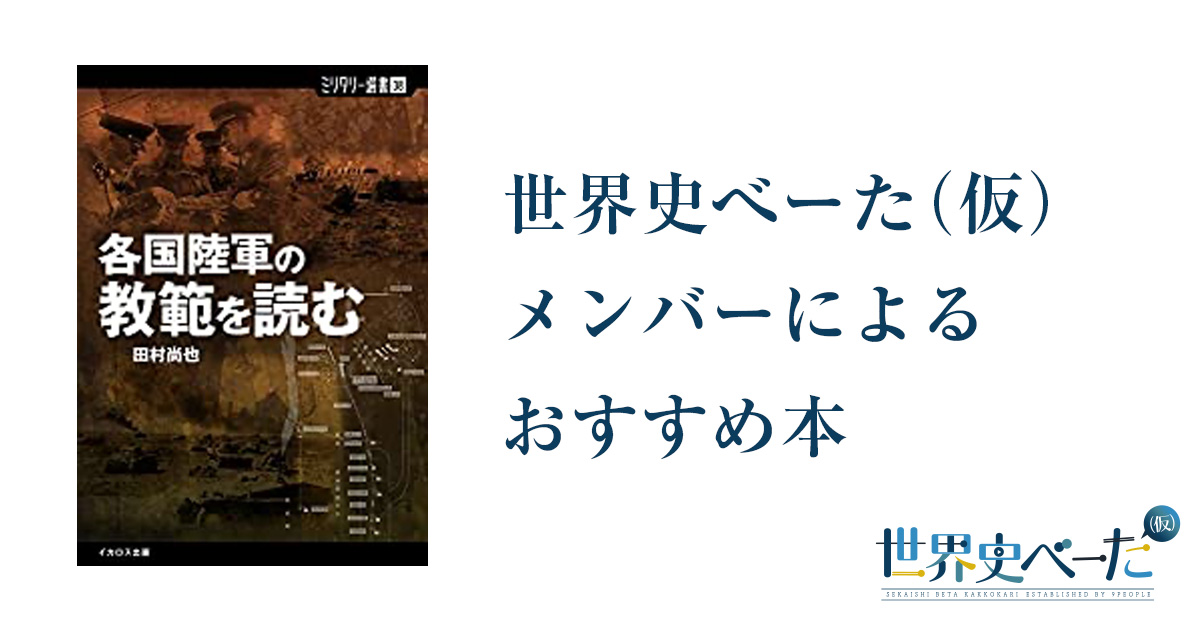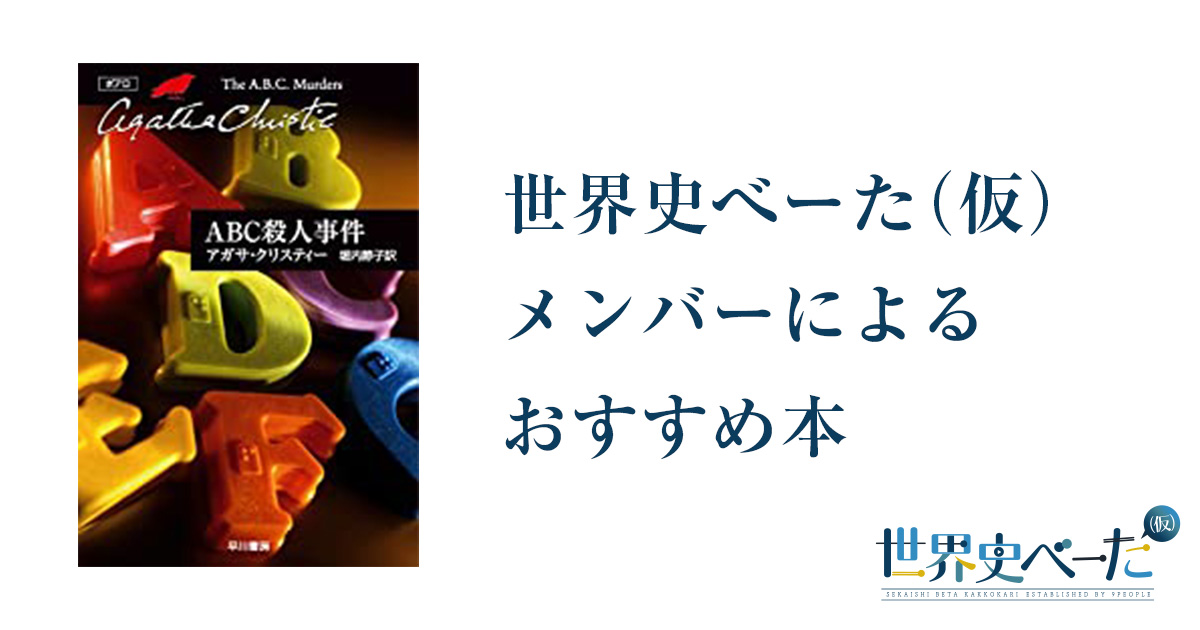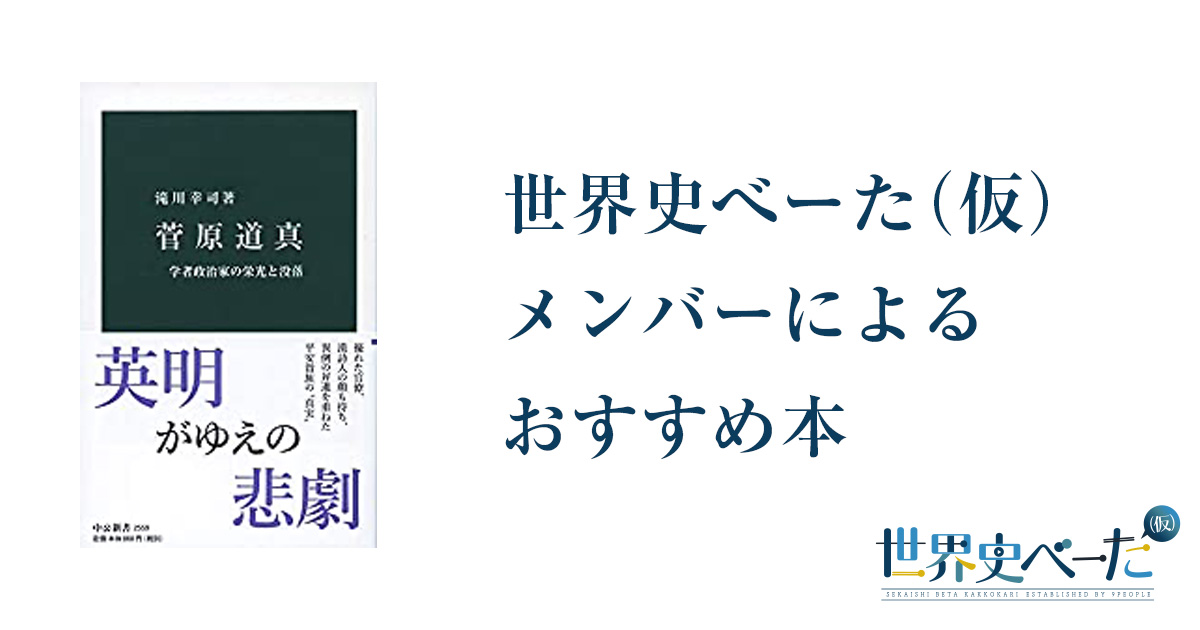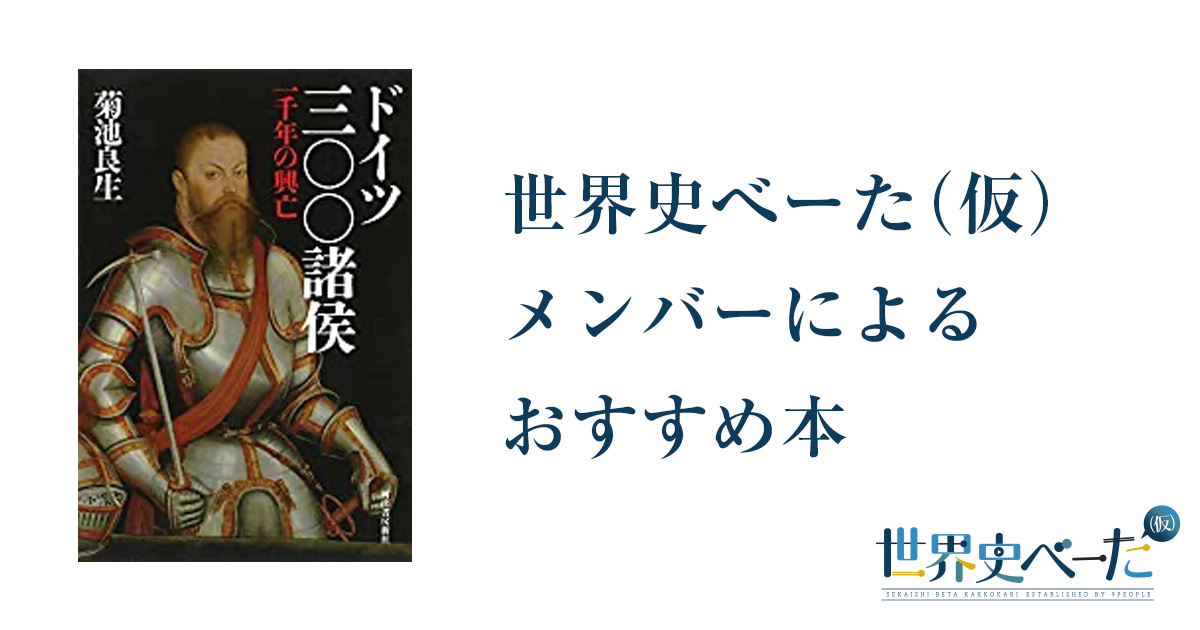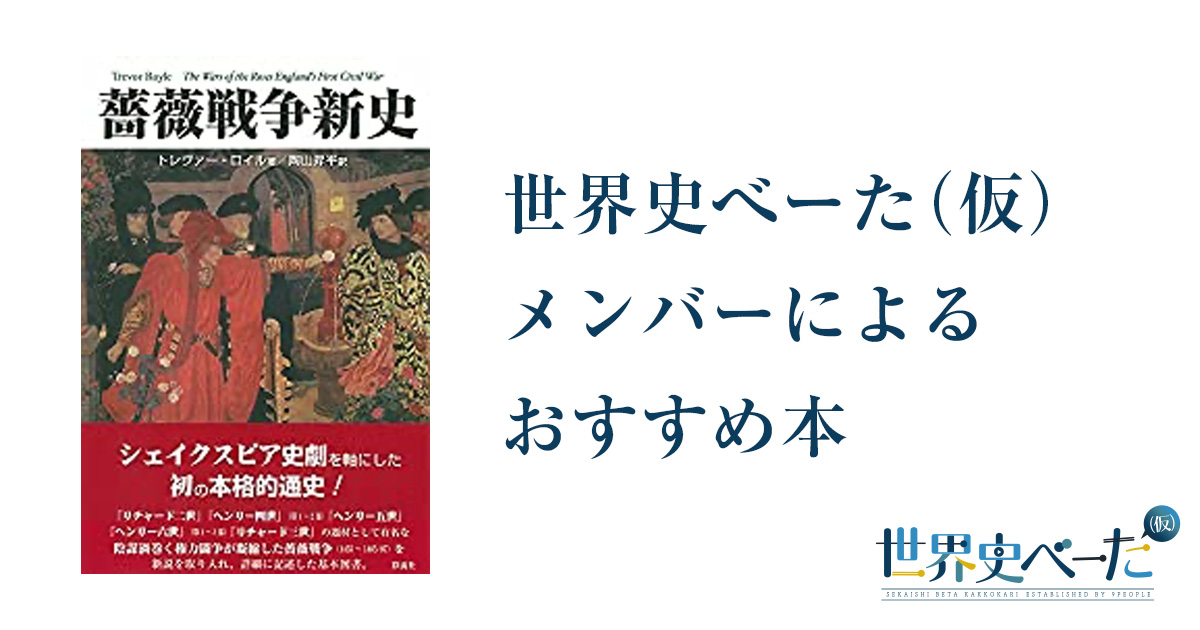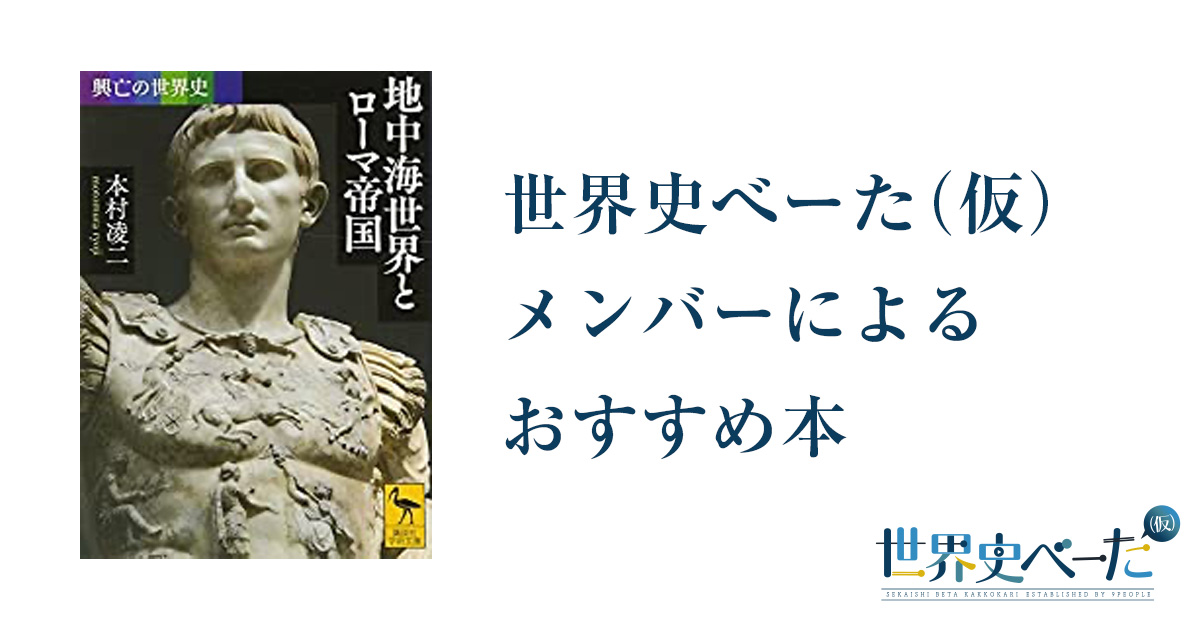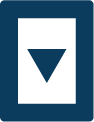さあ前回のブログ(リンク)の続きです! 約1か月ぶりの続編投稿になってしまい大変申し訳ございません💦 「鎌倉弾丸旅行記」は今回がラストになります!✨ 「鶴岡八幡宮」の正門をくぐると正面に広がっているのは参道にあたる「若宮大路」です(何故か写真紛失という大失態💦)。 因みに大路の中央、一段高くなっている歩道は「段葛(だんかずら)」。頼朝が妻・政子の安産祈願の為に御家人たちに築かせた道が原型になっているそうです。 因みにこの「若宮大路」、ただの一本道というわけではなく、八幡宮側に近づくにつれて「道幅が狭く」なっております。「遠近法」を利用して実際以上に距離を長く見せているとか。ほえ~ それはさておき、一旦八幡宮の東側に徒歩で向かいます。「頼朝時代の御所(大倉幕府)」があった方向ですね(現在は小学校になってます♪)。 というわけでまずは「源頼朝」のお墓(いきなりのビックネーム)! 住宅地の奥にある丘の上、そこまで目立つ場所ではなかったのですが、大勢の観光客の方がいらっしゃってました。大河パワー恐るべし!✨ 更にその付近には「北条義時」や「大江広元」など御家人たちのお墓がありました! 反抗的な御家人たちが多い中(ドラマ設定)、頼朝を献身的に支えている御二方は、今でも鎌倉殿の側で眠っているんですね♪ 主人公の義時は勿論、広元もドラマ終盤まで活躍する重要人物ですのでこれからの活躍に注目です! さあ、次は八幡宮を挟んで反対側(西側)に徒歩で移動します。そろそろ足が悲鳴を上げ始めました…💦 次の目的地は鎌倉五山の第三位「寿福寺」です。 「北条政子」が、頼朝の父「源義朝」の館があった場所に建てた禅宗のお寺です。(例によってコロナの為に御朱印は頂けませんでした…) このお寺には「北条政子」とその次男「源実朝」のお墓があります(裏手の山腹)。頼朝と違う場所にお墓があるのはちょっと意外でしたが、息子と一緒なら寂しくないでしょうね。 頼朝夫婦は八幡宮を挟んで東西から今でも鎌倉の街を見守っているのでした(しみじみ)。 最後に徒歩で向かった(本日最長の距離)のは、有名な「鎌倉大仏(高徳院)」です。 鎌倉を代表する寺院ですが、実は誰がどういった経緯で建立したのかよく分かっていないミステリアスなお寺だったりします(鎌倉時代に建てられたのは間違いないようです)。 あと現在大仏様は野ざらしですが、かつては大仏殿があったそうです。 この時点で足は限界、時間も迫っていましたので今回の「鎌倉弾丸旅行」は終了となりました💦(心地よいクタクタ)。 それぞれの場所は巡って歩き回る間にも「和田義盛」や「畠山重忠」など大河ドラマにも登場する人々ゆかりの地を偶然発見するなど、街中至る所が歴史を感じる場所で、九州民の私としては非常に貴重で楽しい時間を過ごすことが出来ました♪✨ 実は、今月末に再び関東への出張が決まっておりまして、その際はまた「旅行記」のようなもの執筆できればと思っています。 それでは今回はここまで。 最後までお読みいただきまして、本当にありがとうございました!✨ 〇(><)
Category: 執筆者
道真第二回の参考文献と、寛平遣唐使問題の諸説
文人官僚の限界を超えて♪ 道真は来たんだよ おひさしぶりです。「みっちざねにしてあげる♪(してやんよ)」という曲(捏造)が頭から離れない※(米印)です。 菅原道真解説の第二回、ご覧いただきありがとうございます(見ろよ、という圧)。 さて、今回は文献紹介と補足解説を行っていきます。前回も言いましたが、私は平安期日本史の専門家ではありませんので、参考程度にしてくださいね。 参考文献紹介 渤海使関連 上田雄(2004)『渤海国 東アジア古代王国の使者たち』講談社学術文庫。 ※文庫本なのでお手軽。渤海使の基礎情報はほとんどこれが網羅しています。ちなみにこれは1992年の『渤海国の謎 知られざる東アジアの古代王国』(講談社現代新書)を元にした本なので、どっちかが見つかればぜひ読んでください。 古畑徹(2018)『渤海国とは何か』(歴史文化ライブラリー 458)、吉川弘文館。 ※渤海の国自体についてはこれがおすすめです。ただ、渤海使についてはそこまで詳しく扱っていないのです…… 上田雄(2002)『渤海使の研究 日本海を渡った使節たちの軌跡』明石書店。 ※専門書です。各回の渤海使(違期入朝含む)を詳細に記しています。ちなみに都言道くんの下心もこれのおかげで知りました。 寛平遣唐使問題 渡邊誠(2013)「寛平の遣唐使派遣計画の実像」『史人 5号』広島大学大学院教育学研究科下向井研究室。 ※論文です。増村~石井の議論がよくまとまっています。寛平遣唐使問題に興味を持った方はまず読んでみてください(リポジトリに公開されているので無料で読めます) 石井正敏著、村井章介、榎本渉、河内春人編(2018)『遣唐使から巡礼僧へ』(石井正敏著作集 第二巻)、勉誠出版。 ※石井の論文集です。「いわゆる遣唐使の停止について」と「寛平六年の遣唐使計画について」、それから「寛平六年の遣唐使計画と新羅の海賊」が寛平遣唐使問題を扱っています。「いわゆる~」は「其日」問題、「~新羅の海賊」は「新羅賊」説まわりの否定なので、もし個別に論文を探すなら「~計画について」(道真の二つの文章の読解)をどうぞ。 増村宏(1988)『遣唐使の研究』同朋舎出版。 ※結構古いですが、だいぶ先進的な議論を行っています。ただし、他説批判がメインなので増村自身の説は見えにくいかもしれません。だいたいの古い説は「増村を見ろ」で終わります(え 滝川幸司(2019)「菅原道真と遣唐使(一) 『請令諸公卿議定遣唐使進止状』『奉勅為太政官報在唐僧中瓘牒』の再検討」『詞林 65』大阪大学古代中世文学研究会 滝川幸司(2020)「渡唐の心情は詠まれたのか 寛平の遣唐使と漢詩文」『語文 115』大阪大学国語国文学会。 ※滝川先生の論文です。直前までこれに気づかずに作ってしまって、「まぁどうせそんな変わらんやろ」と読んでみたら論理でぶん殴られてしましました。上のやつはweb上で公開されてますので、ぜひ読んでみてください。 道真の再検討要請の理由の諸説(紹介しきれなかったもの) 鈴木靖民の「新羅賊」説 石井らが否定。そもそも、史料を素直に読めば道真が理由にしたのは「唐に着いてからの困難」だったはずなので、唐に着く前(渡航)を問題にするのはナンセンスだと私は思う。 「大義名分説」や「社会経済説」などなど。 増村によくまとまってるからそっちを読んでください……でよろしいでしょうか。早期の説なのでちょっと…… 「藤原氏陰謀説」 藤原氏が道真を遠ざけようとして、というのは明らかに無理筋。ただし、個人的には、本編で述べたような「意思疎通不足」は陰謀に求めることもできなくはないのかなと思ったり。というのも、道真は結構全方面から嫌われていたので(悲しい)、宇多の近臣に道真を疎む者が居てもおかしくはない。ただ、あえて陰謀があったと考える必要性は薄いと思う。 ほか、私の個人的な雑感 滝川は遣唐使再検討の根拠は「中瓘の録記」と断じているが、個人的には早計な感がある。道真が個人的に持っていた伝手を辿ったり、(場合によってはあまり公にできない)商人などから得た情報をもとにしていた可能性は考えられる。その場合は森説に近いものがあるのかもしれない。 ただ、中瓘録記未読説を取らないなら、中瓘の録記で既に渡唐停止を勧めているわけで、それ以上に何か決め手となる情報とは一体なんぞや、という疑問は残る。やはり本編で出したようなコミュニケーション不足に求めた方が無難な気が……しかし根拠はないわけで。やっぱりわからん。 今回は寛平遣唐使問題をかなり深堀りできたと思います。たぶん最新研究とそこそこ同じ景色が見られているのではないかと。ただ、そのせいでちょっと次回の目途が立っておりません……6月に投稿できたらいいなぁ……(そして今回に比べたら薄味でも許して下さい。むしろ今回が異常なんです)
各国陸軍の教範を読む
各国陸軍の教範を読む 教範とは、各国の軍隊が編纂する教科書・マニュアルのようなもので、 各国の軍事行動のドクトリン(基本的な思想・原則)が反映されている。 したがってこの教範を読めば、その軍隊の戦術教義を理解することができるのである。 本書では、第二次大戦までに編纂されたドイツ、フランス、ソ連、日本の各陸軍の、 師団から軍レベルの運用に関する教範を平易に読み解き、行軍、捜索、攻撃、防御などそれぞれの局面で、 各国軍がどのような戦術に基づいて戦おうとしていたのかを探っていく。 各国軍の戦術の基本となった「教範」から第二次世界大戦の陸戦を研究する一冊である。 理解を助ける図版・図表など40点以上を収録。 おすすめ本です 近代軍事史において、なぜドイツが電撃戦を採用し、なぜソビエト軍は縦深戦術を採用したのかというのがこの「教範」を読むことである程度理解することができます。つまり、各国の戦術志向の根幹を知ることができるのです。これを知っているか、知らないでいるかで「戦史」というものの見方はそれなりに変わってくるかもしれませんね。 書籍情報 著者:田村尚也 翻訳者:– 編集者:– その他:– 出版社:イカロス出版 出版年:2015/9/10 ISBN-10:4802200633 ISBN-13:978-4802200639
ABC殺人事件
ポアロのもとに届いた予告状のとおり、Aで始まる地名の町で、Aの頭文字の老婆が殺された。現場には不気味にABC鉄道案内が残されていた。まもなく、第二、第三の挑戦状が届き、Bの地でBの頭文字の娘が、Cの地でCの頭文字の紳士が殺され……。新訳でおくる、著者全盛期の代表作。 【アマゾン書籍情報から引用】 推薦タイトル 有名な作品なので呼んだことがある人も多いのではないでしょうか。私も小学生の時に児童書で呼んだことがあり、予告状が名探偵ポアロに送り付けられたりするところは、ワクワクしました。 少 しネタバレになってしまいますが、「殺人を隠すために、別の殺人をするという」というトリックはこの作品が初めてだと言われています(厳密に言うと、チェスタトンの「折れた剣」にも似たようなトリックがでてきますが) あと、この作品ではクリスティはこいつ犯人だろうというブラフをかけておきながら、最後にどんでん返しを用意しています。ぜひ呼んでみてくださいね♪ 書籍情報 著者:アガサ・クリスティ 翻訳者:堀内 静子 編集者:– その他:– 出版社:早川書房 出版年:2003/11/10 ISBN-10:4151300112 ISBN-13:978-4151300110
皆さんは「猫島国」を知っていますか?
はじめまして、ゆはると申します。まずは自己紹介をさせてください。 私は2019年よりニコニコ動画・Youtubeにて国をテーマにした現代史動画を投稿する活動をしています。現在までにアルゼンチン、アルバニア、ユーゴスラビア、ベラルーシなどの動画を作りました。 2022年からは新たなチャレンジしてみようということで、頭の中で色々な構想を練っていたところ、世界史べーた(仮)という面白そうなサークルが活動を始めることを知り、飛び乗り参加させていただきました。 実は大学の専攻は歴史学とは異なるものだったりするので、世界史べーた(仮)の錚々たるメンバーのオーラにやや気圧され気味ではありますが、自分の作りたいものを表現すべく活動していきますのでよろしくお願いします。 さてここから本題ですが、皆さんは「猫島国」を知っていますか? まず日本には猫島と呼ばれる、たくさんの猫たちが暮らしている島が多数存在します。有名なのは宮城県石巻市に属する田代島、都心からのアクセス抜群な神奈川県の江ノ島、瀬戸内海に浮かぶ愛媛県大洲市の青島などなど。ネコちゃんじゃないですがうさぎの島である大久野島も有名ですね。 今ご紹介したどの島も人より猫の数の方が多く、まさに猫島なわけですが、世界には人よりも猫の数の方が多い「国」があります。その中の一つが地中海に浮かぶ島国、マルタ共和国です。 歴史に詳しい方であればマルタ共和国がどこに位置し、どのような過去を持つかなどはご存知だと思いますが、この国には教科書の上では語られない魅力(主に猫)で溢れています。コロナ禍前の2019年に行ったマルタ旅行を思い返しながら少しだけ紹介します。 ・いたるところにいる猫 (写真ACより「マルタの猫」 by naoko429さん) 天気が良い日であれば、街を歩くとよく猫と遭遇しました。日本で目にする野良猫と比べ、かなり人懐っこい性格の子が多く、エサを持っていた時はたくさんの猫に囲まれるということもしばしば。 ・街の猫スポット (写真ACより「マルタの猫公園」 by omochimochimochiさん) 街の中心部にある「猫公園」にはたくさんの猫がいました。マルタの猫は綺麗で健康そうな子が多く、聞いたところによると地域住民がボランティアとして猫の餌付けや健康管理などをしているそうです。 ・街がそのまま世界遺産のバレッタ市街 (写真ACより「マルタ ヴァレッタ 対岸からの景色2」 by じむにいさん) マルタ共和国の首都であるバレッタの市街は街がそのまま世界遺産(文化遺産)になっています。歴史的建造物が立ち並ぶ中を歩くと中世ヨーロッパに迷い込んでしまったかのような感覚を味わえました。 ・ご当地炭酸飲料の「Kinnie(キニー)」 (筆者撮影) マルタの国民的炭酸飲料として紹介されたのが、オレンジの皮を原料として作られたキニーです。ガイドさん曰く、美味いと感じるか不味いと感じるかは半々で、飲んだ人の意見は真っ二つに分かれるとか。飲んだ感想としてはオレンジ版のドクターペッパーといった感じでした。ちなみに自分は美味しく感じる側の人間でした。 こんな感じでマルタについて語ってきましたがいかがだったでしょうか。実はマルタ旅行の際に撮影したビデオが大量に残ってて、いつかマルタ紹介のボイロ動画を作れたらいいなぁ~とか思っています。 まだまだ自由に海外旅行ができない情勢が続いていますが、可能になった際はぜひマルタに行ってみてください。それでは。
菅原道真-学者政治家の栄光と没落
学者ながら右大臣に昇進するが、無実の罪で大宰府に左遷された菅原道真(845~903)。藤原氏の専横が目立ち始めたこの時期、学問を家業とした道真は、英邁で名高く、宇多天皇に見出され異例の出世を果たす。天皇による過大な評価・重用に苦悩しつつも、遣唐使派遣など重大な国政に関与。だが藤原氏の策謀により失脚する。本書は、学者、官僚、政治家、漢詩人として、多才がゆえに悲劇の道を辿った平安貴族を描き出す。 【アマゾン書籍情報から引用】 菅原道真 濃縮還元100% 道真の人生はどこを切り取っても見どころがあります。私の動画本編でも扱う(予定の)ように、親族、幼少期、出世、外交とのかかわり、そして左遷…… それらを余すところなく、新書一冊にぎゅぎゅっと濃縮したのがこの本です。 新書と侮るなかれ。滝川先生は『菅原道真論』(塙書房)のような専門書も記している、21世紀を代表する道真研究者です。正直なところ、これさえ読んでしまえば道真成分のほとんどは摂取出来てしまうと言ってよいでしょう。 もし、これだけでは足りない、ストレートの道真ジュースが飲みたいんだ、ということであれば、巻末の参考文献や私の文献案内(ダイマ)から色々漁ってみてくださいね。……諭吉が群れを成して逃げ出すのは覚悟の上で(え 書籍情報 著者:滝川 幸司 翻訳者:– 編集者:– その他:– 出版社:中央公論新社 出版年:2019/9/14 ISBN-10:4121025598 ISBN-13:978-4121025593
ドイツ三〇〇諸侯 一千年の興亡
かつてのドイツで300もの領邦に分かれ、繰り広げられた権力争い。破天荒で支離滅裂な諸侯達が跳梁跋扈する激動の時代を活写する。 【アマゾン書籍情報から引用】 神聖ローマ帝国の本 この本のお勧め理由は、とにかく読みやすいことです! 小難しい単語がずらずら並んでて読んでるだけで疲れる類の本ではなく、文字が大きくページ数も多くないです。ただ、内容がガチガチに充実しているかといえばそうではないように感じました。 内容は神聖ローマ帝国内の有名な家系を一章で一家ずつ取り上げているものです。神聖ローマのことについて何か知りたいと言う人には、買って損ではない本だと思います。 書籍情報 著者:菊池 良生 翻訳者:– 編集者:– その他:– 出版社:河出書房新社 出版年:2017/5/26 ISBN-10:4309227023 ISBN-13:978-4309227023
薔薇戦争新史
シェイクスピア史劇を軸にした、わかりやすく本格的な初の通史! 英国初の内戦(1455-1485/87)であり、シェイクスピア史劇(『リチャード二世』『ヘンリー四世』(第1 ~ 2 部)『ヘンリー五世』『ヘンリー六世』(第1 ~ 3 部)『リチャード三世』)の題材としても知られる薔薇戦争を、史劇を足掛かりに、ワット・タイラーの乱、百年戦争、ジャンヌ・ダルクなど戦争期間以外の背景も丁寧にたどり、新説を取り入れながら詳細に記述した英国・欧州中世史・軍事史研究の基本図書。 【アマゾン書籍情報から引用】 おすすめ本です たぶんこれが一番詳しいと思います(日本語では)。 といって私は全部読んだわけではありませんが。やはり歴史をとことん調べるときには一次史料などにあたるのですが、何の事前知識もなく入るのは非常に大変です。読書はステップを踏んで進むものだと思っています。この本は2ステップぐらい踏んだ人が読むことをお勧めします。 本は薔薇戦争の始まる50年以上前までさかのぼって経緯を説明しています。そこまでさかのぼる必要があるほど薔薇戦争は経緯が複雑なものだからです。そもそもランカスター家はなぜ生まれたのか、そしてそこにはどんな問題があったのかを意識すると薔薇戦争は分かりやすくなるでしょう。 ところでプランタジネット朝以降のイングランド史は王に対して次々と有力者たちが行動をエスカレートさせた様子とそれに対し折り合いをつける様子を見ることができます。ヘンリー2世とリチャード1世の時代は王家で争いが起こり、ジョン王の時代には反乱者がマグナカルタを突き付け、ヘンリー3世の時代には反乱者が議会の元を生み出しました。エドワード1世は議会と協力し中世の名君となりましたが、エドワード2世は廃位されて息子が王位につきました。この時イングランドで初めて王が貴族に殺されるのですが、王朝の交代は起こりませんでした。そこから飛んでリチャード2世は子を持たず王朝交代が起こったのですが、このことが50年もたって百年戦争敗戦による諍いが起きたときに利用されたのです。 さて、薔薇戦争は結果として国王の廃位が30年で4回も起こる混乱を引き起こしました。この混乱後はテューダー朝の体制が出来上がるのですが、それも宗教問題で混乱が起こり、引き継がれたステュアート朝では財政問題と合わさって、ついに国王不在の政治体制が出現しました。 イングランドの長い歴史の中で薔薇戦争はどんな意味を持ったのか、そこも考えてみるのも面白いと思います。浅学の身の私ではまだまだ難しいことですが。 書籍情報 著者:トレヴァー・ロイル 翻訳者:陶山 昇平 編集者:– その他:– 出版社:彩流社 出版年:2014/7/24 ISBN-10:4779120322 ISBN-13:978-4779120329
興亡の世界史 地中海世界とローマ帝国
興亡の世界史 地中海世界とローマ帝国 人類の今後を占ううえで、「人類の経験のすべてがつまっている」といわれる古代ローマ史ほど、参考になるものはない。小さな都市国家を強大化に導いた、「共和政ファシズム」の熱狂的エネルギー。猛将・ハンニバルが率いるカルタゴとの死闘。カエサルとアウグストゥスに始まる帝政。地中海はもちろん、ブリテン島から中東にいたる「世界帝国」の現出。そして、ローマ帝国が終焉を迎えた時、古代文明はどのように変貌していたのか。 古代ローマの歴史を知りたい方におすすめ! 古代地中海に君臨した「ローマ帝国」の通史を知ることが出来る一冊です! 「都市国家から始まったローマはなぜ地中海の覇権を握るほどの大国に成長できたのか?」 「皇帝が支配する仕組み「帝政」はどのような過程を経て成立したのか?」 「隆盛を極めた大帝国はどうして衰えていったのか?」 そして「帝国が後世に与えた影響は?」 などなど これらの疑問は他の地域や時代の歴史を学んでいく上でも重要なキーワードになると思います。 古今東西問わず、歴史に興味がある方々に是非とも一読して頂きたい一冊です♪ 書籍情報 著者:本村 凌二 翻訳者:– 編集者:– その他:– 出版社:講談社 出版年:2017/9/12 ISBN-10:4062924668 ISBN-13:978-4062924665
はじめまして
せるヴぁんだに関するブログ 第1条 目的 本ブログ記事の目的は、次のとおりである。 せるヴぁんだについて理解すること。そのために簡単な自己紹介を行う。 第2条 せるヴぁんだの定義 せるヴぁんだとは、主としてニコニコ動画において国際法学に関する解説動画の投稿行為を行っている者である。 せるヴぁんだとは、ラテン語の法格言”Pacta Sunt Servanda”-合意は拘束する-からとられたものである。 第3条 過去の投稿動画 代表的なものとして、紲星あかりの3分即決!国際法廷!シリーズなど。 他に、単発モノがニコニコ動画に寄託されている。 3分の題名は、時間概念としての3分に何ら影響を及ぼすものではない。 第4条 今後の方針 国際法全体の解説動画の投稿を試みることに努めなければならない。 前項に並行して、既存シリーズの拡充に努めなければならない。 世界史ベーた(仮)を盛り上げられるように、積極的に貢献するよう努めなければならない。 第5条 コメント このブログは、日本語を正文とし、世界史ベーた(仮)公式に寄託しておく。 というわけで、よろしくお願いいたします。 附則 リンク 3分即決!国際法廷「コルフ海峡事件」 STATE WARS 拒否権の覚醒