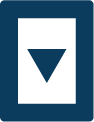メスキィタです。フランスへ行きました。友人がノリで誘ってきたのでこのノリに流されなければいけないと思いついていきました。 まず行ったのはモン・サン・ミシェルです。修道院ですが城壁や塔、城門を備えた立派な要塞です。周囲の景観がなんかイングランドに似ている気がしました。ふもとの町は古き良き時代を感じさせてくれます。ただこの町よりは周囲の農場の方に住んでみたいと思いました。平原が続くノルマンディーの台地で牛や羊を追いながら生活してみたいですよね。本当は大変なんでしょうけど、ちょっと夢見ました。 翌日はヴェルサイユにまず行きました。フランスは何度も行ったことあるんですが同行した友人は初めてなので行きました。誰もが行くヴェルサイユ、言うことはありません。ついでに宮殿の外にあるテニスコートの外観を撮って来ました。 ヴェルサイユ見たら私は一人でフラフラしました。まずはヴェルサイユの前にルイ14世が住み、イングランドから亡命したジェームズ2世も住んだというサン・ジェルマン宮殿。ここは国立考古学博物館となっています。 続いてペール・ラシェーズ墓地。ショパンやシスレーなどの著名人が眠る他、パリ・コミューンが最後の抵抗をした戦場でもあります。 国立技術博物館はいろんな機械の模型があったりします。科学史が好きな方にはお勧めです。 そのあとカタコンブに行ったら改修中だったので、1900年のパリ万博の際に建てられたプティ・パレの美術館で子供の絵を描いた18世紀の画家の特別展を見ました。 翌日はまずルーヴル美術館。ナポレオン3世の部屋が修繕されたというので是非見なければと思いました。モナ=リザ?見なくていいです。私はアモルとプシュケーなら何度見てもいいです。 それからクリュニー中世美術館。ユニコーンのタペストリーで有名なところです。結構前に国立新美術館で見たので二度目の対面でした。 それからアンヴァリッド。ナポレオンの墓がある軍事博物館です。長州藩の大砲を所蔵していることは知っていたので警備の人に聞いたりしたんですがそれは見つかりませんでした。代わりにミトライユーズを見つけて楽しみました。 他にも朝早起きしてしまうのでパリの街を散策したり、余った時間で見ておきたいものを見たりでパリを歩き回っていました。暗い時間帯でもそこまで身の危険を感じずにうろうろできたのは成人男性だからなんでしょう。 とりあえずパリでは見たいものを見たという感じで過ごしました。動画投稿者の性として写真だけは撮りすぎるぐらいには撮りました。フランスなのでイングランド史メインの投稿者としてどの程度使うかはわかりませんけどね。 他には日本でめっきり見かけなくなったオランジーナを飲んだりしてフランスを満喫しました。
Category: 地域
またまた「動画投稿祭」やります!
こんにちは、いのっちです。 師走の候、いよいよ今年も最後の月となりました (誰か嘘だと言ってくれ…) 更に言えば、21世紀も「4分の1」終わりそうってことですね うーん、長かったような、短かったような… もう「2000年に戻る」より「2050年に進む」ほうが近いわけです! さて、チャンネル始動からそろそろ丸4年になるわけですが、 今年もやります。動画投稿祭!(ドン) 「革命祭」、「獣史祭」に続く、 3回目となる今回のタイトルは「金歴祭」です。 今回のテーマは人類史を大きく動かす言動力となった「金」。 もちろん、ゴールドの金だけに限らず、今年も投稿者さんの発想次第では更に動画内容を広げることも可能だと思います。 (金属とか、通貨とか) 私も古代ローマのお金とかで何か作品を投稿しようと考えています。 まずは一年で一番忙しい12月を何とか生き延びねば… 詳しいレギュレーションは「こちら」にまとめておりますが、参考文献が明記されている2分以上の歴史解説動画なら基本的には問題ありませんので、動画投稿未経験の方も気軽に参加して頂けると幸いです。 投稿祭に関する「質問フォーム」も公開しておりますので、疑問点は是非そちらを御利用して頂ければと思います♪ また「X(Twitter)」の方でも積極的に情報を公開して参りますので、フォロー & 拡散に御協力して頂ければ更に投稿祭も盛り上がっていくと思いますのでぜひ応援よろしくお願い致します! アカデミックな年末年始を共に築いていきましょう! 皆さま、よいお年を!
著作権管理団体の起源とStationers Companyについて
漫画村がインターネット上で海賊版ワンピースなどを無料公開していたことは記憶に新しいかと思います。出版物の本質的価値は物質であるインクや紙にあるのではなく、その文字情報や図像ですので、実物をスキャンしてしまえばその「価値」はいくらでも低い労力、コストで複製できてしまいます(発掘現場や工事現場で土の色を記録するときに参照する標準土色帳などのように、画面では再現できない情報のある出版物は別です)。これでは漫画家や作家に報酬を支払い、校正し、自前の販路で出版物を売って新たな作品を生み出すための資金回収などが難しくなってしまいます。こうした問題を解決するために著作権は編み出されました。 著作権は自然状態に存在する権利ではなく、社会がその枠組みを作って、社会を豊かにする著作物をさらに生み出したり、著作者やその関係者の生活を保障するためのものといえるでしょう。そのため初期の出版者や著者たちは自身の利益を確保することに非常に苦労していました。 出版物が無許可に複製されて世に広められてしまうということは古くから問題になっていました。活版印刷普及前は複製が非常に労力のかかる作業で、複写が正確でなかったり、重要でないと考えた場所の複写はしないなどのことがありました。活版印刷の登場は、植字で気を付ければ、正確な複写を大量生産することを可能にし、活版印刷出現当時の印刷業者は今まで写本でも流通していた古典作品の正確な版を生産することに注力していました。こうした事情もあって文芸復興ルネサンスの風潮が生まれたのでしょう。しかし、あらかたこうした古典が図書館や修道院にいきわたると、新しい書物の生産が盛んになります。このころにはロンドンの出版業者は組合でまとまっており、イングランドではこの組合以外の出版業者は撤退していました。この組合がステーショナーズ・カンパニーです。 彼らは互いの利益を守るために書籍の台帳を持っており、組合内(つまりイングランドの全出版業者)でその台帳の書籍は決まった版元だけが複製することができることになっていました。こうした利益確保がのちの著作権の概念につながっていきました。やがて版元がその権利を相続するなどするときにまた問題が発生するのですが、今回はここまで…
私にとっての戦争話
どうも皆さんこんにちは、いのっちです! いや~、今年も半分終わりましたね(絶望) 九州は既に梅雨が明け、気温もぐいぐい上がっています(絶望) さて、夏の足音が近づいてきた(というかグイグイ迫ってきた)ので、 今年で80年目を迎える「あの戦争」を振り返ってみたいと思います。 といっても、当然私は生まれていません(平成生まれ)ので、 戦前生まれだった祖父母たち(全員既に他界)から聞いたお話を、 祖父母たちの冥福を祈り意味も込めて記していきます。 【父方の祖父】 私が生まれた頃には既に定年を迎えており、杖を突きながら趣味の畑に勤しむ姿しか記憶にありません。 ただ子供の頃にいじめられた時、父親から日本刀を渡されて「仕返しするまで帰って来るな!」と言われた話(当然未遂)を笑いながら語ってくれたので、後述のエピソードからも合わせて「豪胆な人」だったのかなあという今更ながら考えています。 終戦時は20歳だった祖父は、理系出身だったためか徴兵を免れ、 戦時中は九州のとある工場に動員されていたそうでして。 ある時、工場内での待遇に不満を抱いた同僚たちを引き連れて勝手に実家へ戻ったというエピソードを教えてくれました。 (そんなことしたらただでは済まない気がするのですが…) あと、広島や長崎に「原爆」が投下された頃は「小倉(福岡県北九州市の地名)」にいたそうでして… 有名な話ですが、小倉は原爆投下の候補地になったいたのですが、たまたま雲に覆われて街が視認できなかったため難を逃れた場所です。 もし小倉が晴れていたら、私は生まれていなかったでしょう。 この世に生を受けるのは将に奇跡の積み重ねだと実感します。 【父方の祖母】 祖母は結構裕福な家庭だったらしく、戦争中は「満州」に一家で移住しており「鞍山女学院」という学校に通っていたそうです。 (晩年まで女学院の同窓会に出席していたので、やはり思い入れが強かったんでしょうね) 終戦間近、満州にはソ連軍が北から侵攻してくるのですが、幸いなことに祖母一家がいた場所は南側だったため、終戦時は直ぐに本土へ引き上げることができたそうです。 もし、満州の北側にいたら… この世に生を受けるのは将に奇跡の積み重ね(二度目) 【母方の祖父】 祖父も「満州」に縁のある人でして、農家の次男だったため「口減らし」の意味も込めて、父親から無理やり「満蒙開拓団」に入れられたと語っていました。 毎晩、親を恨んで泣いていたという思い出話には胸が締め付けられました… 因みにその影響で、晩年足腰が弱り、今朝の朝ごはんを思い出せない状態でも満州の地名はハッキリと覚えていました。 両手に杖を突き、行進曲?を口ずさみながら自宅の庭を散歩していましたね。 幸いなことに終戦前には九州に帰還しており、玉音放送は農作業に出かけていたため聞いていなかったとか (帰宅して戦争が終わったことを知ったと言ってました) … Continue reading 私にとっての戦争話
◉平野耕太★大博覧會に行ってきました❤︎(後編)
こんにぢは!!!!! どうもフォンスティーヴです。 デン!(和太鼓の効果音) 前回の続きということで今回は平野耕太★大博覧會のドリフターズ回廊と買ったグッズをお送りしていこうと思います! 島津豊久の巨大パネルを超えると1600年関ヶ原の戦いのジオラマが!! ここからドリフターズが始まるんですよなぁ さらに進むと紫のオフィスがお出迎え この扉のうちの一つを潜って次の回廊に行く作りになっているのも超興奮しましたッ…… 織田信長と那須与一の御登場!!!!! ヘルシング回廊と同様に各所にキャラクター紹介&名言パネルも点在してました! サンジェルミ伯結構好きなんですよねぇ 土方歳三と島津の再現コスチューム! ^^; そして最後にはドリフターズのキャラたちの歴史年表がドン!!!! ハンニバルやナチスはもちろん、作中で名前だけしか登場していないテーベの神聖隊まで御丁寧に活躍年代が記載されてました(笑) そして今回の戦利品はこちら!!!(デデン) 島津豊久、菅野直、そしてアーカードの陶器製マグカップとドリフターズキャラクター紹介の湯飲み!! 更にアンデルセンのシガーケースと島津豊久ZIPPO! 本当はアーカードのZIPPOとかシガーケースとか欲しかったんですけれど私が会場に訪れる頃にはとっくに売り切れていました;; でもどのグッズも良心的価格な上に未だに現役でバリバリ使えてるほど耐久性もバッチリです👍 何を取っても楽しかったという感想しか出ない大博覧會でしたッ……。 それではまたこんど!!!!!!
『坂の上の雲』はいいぞ。(おすすめ歴史ドラマ紹介 特別編)
※とある歴史ドラマの紹介文です。ネタバレ注意! こんにちは、いのっちです! 新年度も「世界史べーた(仮)」をよろしくお願い致します♪ (「獣史祭」への御参加 & 応援ありがとうございました!✨ 再生リストはこちら♪) さて、今回は久々に「歴史ドラマ」の御紹介をさせて頂きたいと思います (今回で6本目、約1年ぶり)。 過去の紹介ブログはこちら! ⇒ 第1回「草燃える」 第2回「花神」 第3回「翔ぶが如く」 第4回「毛利元就」 第5回「葵徳川三代」 今回は、3月に再放送が終了したばかりの『坂の上の雲』(2009年[平成21]~2011年[平成23])を御紹介したいと思います。 (※あくまでドラマ紹介ですので、史実や原作とは微妙に内容が違う可能性があります) 何といっても、懐かしかった(もう15年前…) 本放送の頃の私はまだ子供でしたので、続きが待ち遠しくてうずうずしていたことを思い出します。 (本作は1年おきに放送される3部構成でした) いわゆる通年で放送される「大河ドラマ」枠ではありませんが、放送時間は大河の倍(90分)で、膨大な制作費を費やして世界中でロケを行うなど、「NHKの本気」を垣間見ることが出来る超大作の「スペシャルドラマ」です。 (旅順港閉塞作戦や二百三高地、そして日本海海戦は大迫力) 加えて、大河常連のベテランや大物俳優さんたちが惜しみなく出演されており、この規模の歴史ドラマは正直二度と制作できないのではないのかと寂しく感じた自分もいました。 (もちろん、いつか超える日が来て欲しいです!) 物語(史実と区別するためにあえてこう呼びます)の舞台は「明治時代」の日本です。 主人公は伊予松山(現在の愛媛県松山市)出身で、「智謀如湧(ちぼうわくがごとし)」と称えられた海軍軍人「秋山真之(演:本木雅弘さん)」、その兄で「日本騎兵の父」と呼ばれた「秋山好古(演:阿部寛さん)」、そして真之の親友で明治を代表する俳人「正岡子規(演:香川照之さん)」の3人です。 …ということになっていますが、実際には政治家、軍人、文化人、そして一般の民衆に至るまで、明治という新時代を築いていった人々を描く群像劇となっているのが本作の特徴です。 (もちろん物語の中心は彼らですが) 原作者の「司馬遼太郎(大正生まれ)」は、明治という時代に「庶民が国家というものにはじめて参加しえた集団的感動の時代」、「個人の栄達が国家の利益と合致する昂揚の時代」、「楽天的な時代」など、かなり好印象を抱いていたと思われます。 国家・国民が一丸となって国威発揚に向かっていく姿は「昭和後期の高度経済成長期」に重なるイメージかもしれません(いわゆる「昔はよかった」的なノスタルジー史観) まあ、司馬さんは戦争を経験している世代(終戦時22歳、従軍経験有り)ですし、日本史に対する関心の出発点(創作意欲の源泉)がまさに昭和の軍部に対する失望(「昔の日本人はもう少しましだったのでは?」)だったわけなので明治の理想化は仕方ないと思いますが。 もちろん近代化の進展で生じた様々な悲劇や苦難などもあったわけで、ドラマではその辺りに触れるシーンが挿入されていました。 本作には様々な魅力的な人物が登場するのですが、流石に全員紹介すると長くなりますので、何人かを個人的にピックアップして御紹介しますね♪ (お気に入りの方に言及していなかったらすいません…) … Continue reading 『坂の上の雲』はいいぞ。(おすすめ歴史ドラマ紹介 特別編)
理神論争~神を理解せよ~その政治的背景を少し
貴方は神を信じますか?今でこそ「別に信じていない」と言えるのですが、17世紀のイングランドではそんなこと言えません。当時はみんな神を信じていますし、多少疑問に思っていても常識のある人なら神を信じているような発言をしたものです。ところで、かつては人間ごときに理解できないと考えられていたあまりにも偉大過ぎる神ですが、フランシス・ベーコンやデカルトなどによる科学革命が進行し、17世紀の後半では「世界は理性でとらえられるものだ」という考えが次第に力を増していました。ニュートンの万有引力の法則が星空も地上と同じ法則によって動いていることをあかしたというのはその成果の一つです。他方フランスでは月の圧力が潮の満ち引きを引き起こすと考えられていましたが、少なくとも神を安易に用いない説明を世界に対して向け始めたことが重要です。 こうした科学的な思考の黎明期にあっても神の存在は当然信じられていました。当時は神を理解するために自然を探求していたからです。ニュートンも世界を創造した神にとって空間は感覚器官であり、時折この世界に干渉すると述べています。反発した人々は「時折介入しなければならないのは全能の神にしては不完全だ」と反論しています。こうした反発者にとって神は時計職人のようなものでした。完璧な世界という時計を作った神は、その見事な調和が動き始めてからは、介入せず、それでも世界は動くと言う考え方です。神の存在を証明する試みもこの時期にデカルトやスピノザによって理性的に試みられます。ここでは何が重要かと言うと、人間が神を理解しようと試みたことです。人間の思考が及ばないような次元にいるとは考えていないのです。もちろん多くの人は昔ながらの、人の理解の及ばない全能の神を想像したのでしょうしが、知識人には神を理解したいという欲求が沸いていたのです。 神を理性で理解する試みは政治的な要因も働いていました。イングランドの宗教は国教会ですが、この教会は多くの人々を包摂するために、教義にはゆとりがありました。そこには従来のカトリック的な啓示(限られた人の前のみに明かされる神の言葉)や儀式を重んじる高教会派と、聖書を重視するプロテスタントの原則に近い低教会派がありました。この二つの派閥の争いで、高教会派はある程度まとまりをもつ中、低教会派は国教会からも除外された派閥とも交流を持ちました。この除外された派閥とも交流を持つことで広く仲間を募る広教会派が生まれるのですが、何しろもともと意見が違って別派閥になったのですから団結力に欠けます。そこで彼らの思想の中心に自然神学、つまり啓示に頼らずに理性で神を理解しようとする考えが据えられたのです。 高教会派と低教会派はトーリーとホイッグに結びついています。カトリック的要素のある高教会派はトーリーに属するわけですが、トーリーはカトリックを公言するチャールズ2世の弟の王位継承を支持していました。当時彼の王位継承は国を二分する争いになっていて、カトリック嫌いなイングランド人としては伝統に反してでも弟の王位継承を避けるべきか、伝統にのっとるべきかで割れていたのです。ホイッグは低教会派、広教主義でしたが、伝統の強い力に対抗するためにも理性を持ち出す必要があったのでしょう。 と、まとまったようなまとまってないような話は以上です。
好きな歴史上の人物というのは、好きな架空のキャラクターと同じではないか?
「歴史好き」と「歴史学者」の違い ※随筆です。敬仲の他の記事と異なり、本記事には学術的根拠はありません。 先日ツイッター(現X)にて、ある興味深いツイートを見ました。 ある歴史研究者の引用の言葉の引用として歴史学者は歴史上の特定の人物への尊敬、心酔、共感といった個人への崇拝や愛着から距離を置くべき と書いてあったのです。 (投稿主様および、発言主の歴史学者の方への迷惑となるやもしれませんので、リンクは控えます) さらに投稿主様はこれを、「歴史好き」と「歴史学者」の違いとおっしゃっています。 この両者の違いは以前に「歴史が好きだから史学科に行く?」という配信をしたように、当チャンネルにとって重要な議題ですね。 さて、ツイッターに戻ります。これを見た瞬間、私は「その通りだ」という賛同と「それはどうかな?」反対という全く別方向の感情が同時に生じました。 それは何故か? まず私は「文学」・「思想哲学」の徒であって、「歴史学」の徒ではありません。 「歴史好き」と「歴史学者」の中間といか、この両者のX軸上は中間ですが、Y軸方向にずれているとでもいいましょうか。 歴史上の人物が登場する古典や、歴史上の人物の著作物を好みます。 歴史学の研究成果を参照しますし、歴史学に片足を突っ込んだものを研究対象とすることもあります。しかし特定の著作者、あるいはその著作物を研究対象とすることが基本となります。 よって、ある文学者の作品を正確に理解する、ある思想家がなぜその思想を着想できたのか探る、そのためには尊敬や心酔はともかく、少なくとも「共感」は必要ではないでしょうか。どういう空間的・時間的で状況でそれを書いたのか探るわけですから。 そもそも、研究対象の人物の著作を全部読み込むというような研究の前提となる作業をするには、愛着がなくては不可能でしょう。その著作物を素晴しいと思っていなければ、丁寧には読めないでしょう。「共感」には誤読を防ぐ役割があります。 その故に、「歴史学者」といえど、特定の個人に対して思い入れを持たないことが100%正しいことと言えるのかな?という疑問が生じました。 一方で「歴史上の特定の個人」を好きだというのは、適切な研究姿勢であるためにという以前に、極めて不確かなことだと考えています。 「好きな歴史上の人物」は誰?という質問 私はたまに「好きな歴史上の人物」を聞かれることがあります。歴史ファンほか、人から歴史に詳しいと思われている人なら一度は聞かれたことのある質問でしょう。 (人物というか「武将」という聞かれ方が多い気がしますが) この質問には非常に回答に困ります。 おそらく聞く人は「好きな歴史上の人物」について、偉大な帝王や武将を名前を期待する方するでしょう。しかし、そうした人物の事跡はともかく、日常での発言や行動は様々な脚色された話が多量にくっついていて、その人の実態を把握することは困難です。本当に実態をつかみ取れるのはここ数十年の人物だけではないでしょうか。 また、「好きな歴史上の人物」へいだくイメージを、小説やドラマといったフィクションを排除してもつことは難しいのではないでしょうか。 つまり、「好きな歴史上の人物」というのは「好きな架空のキャラクター」とほとんど変わらないのではないでしょうか? 好きな人物はフィクションにまみれているが、著作物には当人が現れているのでは? 具体例をあげてみましょう。私は中国文学は大学での専攻領域の一部であり、かつ『三国志演義』のファンです。 故に「好きな三国志の武将は?」とたまに聞かれるのですが、 小説として聞いてきているのか、歴史として聞いてきてるのか毎回迷います。 そして迷ったときは「曹操」と答えます。 曹操なら小説のキャラクターとしても、歴史上に実在した人物としても好きと言えるからです。 『三国志演義』はもちろん、『世説新語』に面白い話として紹介される曹操は架空のキャラクターになるでしょう。 陳寿の『三国志』とその注釈として引かれる書物に登場する曹操も、どのていど脚色されたものかわかりません。 しかし、彼の著作、詩は本物です。実在した詩人としての曹操のことを好きだということができます。 私にとって儒家思想は、批判的な見方を伴う研究対象であると同時に、近代以前に広くおなわれたよう修身としても学ぶ対象でもあります。 とは言え自身の著作がない孔子や、そもそも創造された堯舜のような聖人たちを私は「尊敬する歴史上の人物」としてあげることはできません。 しかし優れた著作のある朱子や王陽明は私にとって「尊敬する歴史上の人物」ということができます。 (彼ら自身というよりは、彼らの考えたもの、作ったものへの尊敬といった方が適切かもしれません。) とは言え『荘子』には「書物に書かれたことなど、『古人の糟魄(このりカス)』だ」という説があります。 著作物は哲学者、文人の全てを詰め込んだものではなはありません。神髄といえるものがどれだけ書物にあらわれているかは不確かです。さらに現代に伝わる過程で欠けたり、他人が付け足したりということもあります。 好きな歴史上の人物、尊敬する歴史上の人物というのは、好きな架空のキャラクターと同じく、みんなが見たい偶像を見ているだけかもしれませんね。それを言ってしまえば、同じ時代を生きる人、直接言葉を交わす身近な人さえも、全てを理解することはできないのですから。
ウィリアム1世は正しかったのか
イングランド史を学ぶととりあえず大きなターニングポイントとしてノルマン征服を習うと思います。その実行者であるウィリアム1世は武力で王位をもぎ取り、武力で住民を従わせ、戦争の最中に亡くなった、まさにヴァイキングの末裔、天国ではなくヴァルハラが似合う王だったことでしょう。 現代の価値観からすればとんでもない乱暴者とさえ思われるウィリアム1世ですが、そう決めつけてしまうのは全く想像力に乏しく、我々はなぜ彼がその圧倒的パワーを持ちえたのかを考察しなければなりません。多くの地域を支配した歴史を持つイングランドの歴史教育では、この点で執拗に問いを立ててきます。少なくとも私が持っているコリンズのKeyStage3段階の教科書では執拗です。この段階は11-14歳を対象にしたものですが、学習の目標は説明ができるようになることで、例えば「王はなぜ力と対話を用いる必要があったのか」と言う話題について話すことができる、といったものです。少年時代から支配とは何かを学ぶわけですね。 ウィリアム1世がなぜ王位を狙ったのかは聞くまでもないでしょう。私たちが際限なく価値を追求するように、中世の王たちも際限なく価値ある土地を追求します。むしろ狙える土地があるのに狙わなかったことの方が疑問とされるべきことです。戦争を起こしたら犠牲者たちへの説明はどうなるかなど考えません。むしろウィリアム1世はそれによく配慮した側です。彼は教皇から直々に支持を得た聖なる軍を率いたのです。この戦いで死ぬことはキリストのためになり、倒れた相手は不信心者なのです。それに加えて、後継者亡くして死んだ王の親戚かつ友人であり、後継者指名を受けていた(と言う主張)のであり、中世ではウィリアム1世のイングランド王位請求は悪いことなど一つもないでしょう。 神のご加護(彗星の出現、ドーヴァー海峡の天候変化のタイミング、先に競争相手が別で戦う羽目になったことなど、様々な幸運はそう呼ぶほかないぐらいです)で土地を得ましたが、問題はその土地をどう維持するかです。なんと当時のイングランド人500,000人程度に対してウィリアム1世の同胞ノルマン人は10,000人程度、1人で50人の異民族を支配しなければならなかったのです。50人の外国人が働く工場をあなた一人が任されて、彼らに仕事を最大限させるにはどうすればいいのでしょう。機嫌を取ればなめられるだけで相手は要求をエスカレートさせるでしょうし、いつの間にかあなたが彼らの下僕となります。かといって苛烈に扱えば、あなたは工具を片手にした50人から報復を受けるでしょう。ノルマン人は自身の安全を確保するためにまず城を作りました。当時イングランドにはノルマン人が「城」と呼ぶような城はありませんでした(アングロ=サクソン人からしたら城と呼べるものはあったかもしれませんが)。ノルマン人のモット・アンド・ベイリー方式の城郭は当時としては防御が固く、不意打ちを受けないよう住民からは離れて建てられました。こうした恐怖によってウィリアム1世はがちがちに構えてイングランドを支配しました。 優しくスマートに統治するのが理想でしょうが、時には恐怖に頼らざるを得ないこともあるものですというお話です。ウィリアム1世はそのせいか、あまり評判がいい王様ではなく、どちらかといえば侵略者として記憶されていると思います。
フォンスティ音楽教室③ 小澤征爾様について超ざっくり
おひさしぶりでっす。フォンスティーヴ(タコP)です。 大分間が空いてしまいましたね……。 さて、早速前回の続き……と行きたいところなのですが、これを書こうとしたちょうどその時、私の元に衝撃的なニュースが飛び込んできました。あの日本が誇る大指揮者、「小澤征爾」様がご逝去されてしまったと……。 ということで久々の執筆なのですが、少々話題を急カーブさせ、今回は先日お亡くなりになった小澤征爾さんについてお話ししようと思います。 ※この記事には独断と偏見、主観的意見が多分に含まれます。ご了承ください。 先日の小澤征爾様の訃報はネットニュースやメディアでデカデカと掲載されたので目に入った方は多いと思いますが、その中ではそもそも小澤征爾様が何者なのかご存知ない方もいらっしゃったと思います。 小澤征爾(以下敬称略)自体、主に20世紀に活躍された方で、近年では癌の影響であまり表舞台に姿を現していなかったので、おそらく昨今の10代20代の方々は特に知らない方が多いと思います。 小澤征爾は1935年に誕生した日本の指揮者で、おそらく近代日本音楽史の中で最も偉大な人物のうちの1人です。 彼はその生涯で日本人としての様々な偉業を成し遂げていますが、その中で特に偉大なものはやはりニューイヤー・コンサートの指揮でしょう。 クラシック音楽の本場であるオーストリア、ウィーンでは毎年元旦に「ウィーンフィル・ニューイヤーコンサート」と評してコンサートが開かれています。 元旦の「ニューイヤー・コンサート」という名目ではウィーンだけでなくヨーロッパ各地、それこそ日本でも行われていますが、その中でもウィーンフィルニューイヤーコンサートだけは別格で、その場に指揮者として呼ばれるということはクラシック界の中では最高峰の名誉として扱われます。 そして、今までの歴史上そのコンサートに呼ばれた日本人は1人しかおらず、その人こそが「小澤征爾」なのです。 また、それと同じように数十年にも及ぶ長い伝統を誇るフランスのブザンソン国際指揮者コンクールでも日本人として初めて優勝。またドイツやアメリカなど、世界の様々な機関から勲章やメダルを授与されています。現代でも世界で活躍する日本人指揮者は多くいますが、これほどの功績を持った日本人は未だに現れていません。 また、ナチス政権のドイツを生き抜き、20世紀最高の指揮者とも名高い「ヘルベルト・フォン・カラヤン」、同時期のアメリカに生まれ20世紀のクラシック業界の最先端を走り常にリードしてきた「レナート・バーンスタイン」といった偉大な指揮者たちとも親交が深かったことも理由の一つに数えられます。 昭和当時の日本の音楽文化を西洋と対等まで押し上げた立役者の1人だと、筆者は考えます。 小澤征爾様、約半世紀、ありがとうございました。 それではみなさま、ご拝読ありがとうございました。