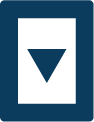漫画村がインターネット上で海賊版ワンピースなどを無料公開していたことは記憶に新しいかと思います。出版物の本質的価値は物質であるインクや紙にあるのではなく、その文字情報や図像ですので、実物をスキャンしてしまえばその「価値」はいくらでも低い労力、コストで複製できてしまいます(発掘現場や工事現場で土の色を記録するときに参照する標準土色帳などのように、画面では再現できない情報のある出版物は別です)。これでは漫画家や作家に報酬を支払い、校正し、自前の販路で出版物を売って新たな作品を生み出すための資金回収などが難しくなってしまいます。こうした問題を解決するために著作権は編み出されました。 著作権は自然状態に存在する権利ではなく、社会がその枠組みを作って、社会を豊かにする著作物をさらに生み出したり、著作者やその関係者の生活を保障するためのものといえるでしょう。そのため初期の出版者や著者たちは自身の利益を確保することに非常に苦労していました。 出版物が無許可に複製されて世に広められてしまうということは古くから問題になっていました。活版印刷普及前は複製が非常に労力のかかる作業で、複写が正確でなかったり、重要でないと考えた場所の複写はしないなどのことがありました。活版印刷の登場は、植字で気を付ければ、正確な複写を大量生産することを可能にし、活版印刷出現当時の印刷業者は今まで写本でも流通していた古典作品の正確な版を生産することに注力していました。こうした事情もあって文芸復興ルネサンスの風潮が生まれたのでしょう。しかし、あらかたこうした古典が図書館や修道院にいきわたると、新しい書物の生産が盛んになります。このころにはロンドンの出版業者は組合でまとまっており、イングランドではこの組合以外の出版業者は撤退していました。この組合がステーショナーズ・カンパニーです。 彼らは互いの利益を守るために書籍の台帳を持っており、組合内(つまりイングランドの全出版業者)でその台帳の書籍は決まった版元だけが複製することができることになっていました。こうした利益確保がのちの著作権の概念につながっていきました。やがて版元がその権利を相続するなどするときにまた問題が発生するのですが、今回はここまで…
Category: ヨーロッパ
理神論争~神を理解せよ~その政治的背景を少し
貴方は神を信じますか?今でこそ「別に信じていない」と言えるのですが、17世紀のイングランドではそんなこと言えません。当時はみんな神を信じていますし、多少疑問に思っていても常識のある人なら神を信じているような発言をしたものです。ところで、かつては人間ごときに理解できないと考えられていたあまりにも偉大過ぎる神ですが、フランシス・ベーコンやデカルトなどによる科学革命が進行し、17世紀の後半では「世界は理性でとらえられるものだ」という考えが次第に力を増していました。ニュートンの万有引力の法則が星空も地上と同じ法則によって動いていることをあかしたというのはその成果の一つです。他方フランスでは月の圧力が潮の満ち引きを引き起こすと考えられていましたが、少なくとも神を安易に用いない説明を世界に対して向け始めたことが重要です。 こうした科学的な思考の黎明期にあっても神の存在は当然信じられていました。当時は神を理解するために自然を探求していたからです。ニュートンも世界を創造した神にとって空間は感覚器官であり、時折この世界に干渉すると述べています。反発した人々は「時折介入しなければならないのは全能の神にしては不完全だ」と反論しています。こうした反発者にとって神は時計職人のようなものでした。完璧な世界という時計を作った神は、その見事な調和が動き始めてからは、介入せず、それでも世界は動くと言う考え方です。神の存在を証明する試みもこの時期にデカルトやスピノザによって理性的に試みられます。ここでは何が重要かと言うと、人間が神を理解しようと試みたことです。人間の思考が及ばないような次元にいるとは考えていないのです。もちろん多くの人は昔ながらの、人の理解の及ばない全能の神を想像したのでしょうしが、知識人には神を理解したいという欲求が沸いていたのです。 神を理性で理解する試みは政治的な要因も働いていました。イングランドの宗教は国教会ですが、この教会は多くの人々を包摂するために、教義にはゆとりがありました。そこには従来のカトリック的な啓示(限られた人の前のみに明かされる神の言葉)や儀式を重んじる高教会派と、聖書を重視するプロテスタントの原則に近い低教会派がありました。この二つの派閥の争いで、高教会派はある程度まとまりをもつ中、低教会派は国教会からも除外された派閥とも交流を持ちました。この除外された派閥とも交流を持つことで広く仲間を募る広教会派が生まれるのですが、何しろもともと意見が違って別派閥になったのですから団結力に欠けます。そこで彼らの思想の中心に自然神学、つまり啓示に頼らずに理性で神を理解しようとする考えが据えられたのです。 高教会派と低教会派はトーリーとホイッグに結びついています。カトリック的要素のある高教会派はトーリーに属するわけですが、トーリーはカトリックを公言するチャールズ2世の弟の王位継承を支持していました。当時彼の王位継承は国を二分する争いになっていて、カトリック嫌いなイングランド人としては伝統に反してでも弟の王位継承を避けるべきか、伝統にのっとるべきかで割れていたのです。ホイッグは低教会派、広教主義でしたが、伝統の強い力に対抗するためにも理性を持ち出す必要があったのでしょう。 と、まとまったようなまとまってないような話は以上です。
ウィリアム1世は正しかったのか
イングランド史を学ぶととりあえず大きなターニングポイントとしてノルマン征服を習うと思います。その実行者であるウィリアム1世は武力で王位をもぎ取り、武力で住民を従わせ、戦争の最中に亡くなった、まさにヴァイキングの末裔、天国ではなくヴァルハラが似合う王だったことでしょう。 現代の価値観からすればとんでもない乱暴者とさえ思われるウィリアム1世ですが、そう決めつけてしまうのは全く想像力に乏しく、我々はなぜ彼がその圧倒的パワーを持ちえたのかを考察しなければなりません。多くの地域を支配した歴史を持つイングランドの歴史教育では、この点で執拗に問いを立ててきます。少なくとも私が持っているコリンズのKeyStage3段階の教科書では執拗です。この段階は11-14歳を対象にしたものですが、学習の目標は説明ができるようになることで、例えば「王はなぜ力と対話を用いる必要があったのか」と言う話題について話すことができる、といったものです。少年時代から支配とは何かを学ぶわけですね。 ウィリアム1世がなぜ王位を狙ったのかは聞くまでもないでしょう。私たちが際限なく価値を追求するように、中世の王たちも際限なく価値ある土地を追求します。むしろ狙える土地があるのに狙わなかったことの方が疑問とされるべきことです。戦争を起こしたら犠牲者たちへの説明はどうなるかなど考えません。むしろウィリアム1世はそれによく配慮した側です。彼は教皇から直々に支持を得た聖なる軍を率いたのです。この戦いで死ぬことはキリストのためになり、倒れた相手は不信心者なのです。それに加えて、後継者亡くして死んだ王の親戚かつ友人であり、後継者指名を受けていた(と言う主張)のであり、中世ではウィリアム1世のイングランド王位請求は悪いことなど一つもないでしょう。 神のご加護(彗星の出現、ドーヴァー海峡の天候変化のタイミング、先に競争相手が別で戦う羽目になったことなど、様々な幸運はそう呼ぶほかないぐらいです)で土地を得ましたが、問題はその土地をどう維持するかです。なんと当時のイングランド人500,000人程度に対してウィリアム1世の同胞ノルマン人は10,000人程度、1人で50人の異民族を支配しなければならなかったのです。50人の外国人が働く工場をあなた一人が任されて、彼らに仕事を最大限させるにはどうすればいいのでしょう。機嫌を取ればなめられるだけで相手は要求をエスカレートさせるでしょうし、いつの間にかあなたが彼らの下僕となります。かといって苛烈に扱えば、あなたは工具を片手にした50人から報復を受けるでしょう。ノルマン人は自身の安全を確保するためにまず城を作りました。当時イングランドにはノルマン人が「城」と呼ぶような城はありませんでした(アングロ=サクソン人からしたら城と呼べるものはあったかもしれませんが)。ノルマン人のモット・アンド・ベイリー方式の城郭は当時としては防御が固く、不意打ちを受けないよう住民からは離れて建てられました。こうした恐怖によってウィリアム1世はがちがちに構えてイングランドを支配しました。 優しくスマートに統治するのが理想でしょうが、時には恐怖に頼らざるを得ないこともあるものですというお話です。ウィリアム1世はそのせいか、あまり評判がいい王様ではなく、どちらかといえば侵略者として記憶されていると思います。
国王陛下戴冠記念第二回イングランド史動画投稿祭参加作品参考文献リンク集
※本ブログはメスキィタ主催による動画投稿祭のまとめ的なものです。投稿祭開催告知動画はこちらです→https://www.nicovideo.jp/watch/sm41574665 ご挨拶 今回も多くの動画投稿者の方にご参加いただけました本投稿祭でございますが、前回よりも参考文献数の多い動画が目立っております。好奇心旺盛な視聴者の皆様方に置かれましては、すべて読んで動画の内容の正否を確認したいと思われることでしょう。しかし、それぞれ文字をタイプして検索するのは大変面倒であります。そこで今回主催が参考文献のリンク集を作成しました。本リンク集をご活用いただき、イングランド史に対する関心が世でさらに高まることを期待しております。 なお参考文献の書式については統一するのが面倒であったので、各投稿者のもの及び、主催者によるフリーダムな書式としました。ネットで無料で閲覧できるものは太字としています。 学生か先生か、学術系データベースにアクセスして情報を入手していると思われる投稿者もいらっしゃいますね。つまり一般人が容易にアクセスできないものも含まれています。 リンク集 【英蘭祭】ケルトの要塞ヒルフォート【VOICEROID解説】 https://www.nicovideo.jp/watch/sm42150520 Hillfort survey – notes for guidance ヒルフォート現地踏査に関する手引書 https://hillforts.arch.ox.ac.uk/assets/guidance.pdf MAIDEN CASTLEについてのEnglish Heritageのサイト https://www.english-heritage.org.uk/visit/places/maiden-castle/ 木村正俊編著『ケルトを知るための65章』明石書店、2018 https://www.akashi.co.jp/book/b351970.html 高野美千代「17世紀好古学文献の変容と読者の受容」『山梨国際研究 : 山梨県立大学国際政策学部紀要』第8巻、2013、pp.46‐pp.56 https://www.yamanashi-ken.ac.jp/media/kgk2013005.pdf 新納泉『鉄器時代と中世前期のアイルランド』岡山大学文学部研究叢書37、2015 https://ousar.lib.okayama-u.ac.jp/files/public/5/53167/20160528120953688360/pso_37.pdf 久末 弥生「イギリスの考古遺産法制と都市計画」 『創造都市研究e』 12巻1号、大阪市立大学大学院創造都市研究科電子ジャーナル、2017 https://e-journal.gsum.osaka-cu.ac.jp/ejcc/article/view/774 Campbell, Lorrae”The Origins of British Hillforts: A comparative study of Late Bronze Age hillfort origins in the Atlantic West”. PhD thesis, University of Liverpool,2021 https://livrepository.liverpool.ac.uk/3135296/ 孫文、清国公使館に囚わる!?~倫敦被難記~【第二回イングランド史投稿祭】 https://www.nicovideo.jp/watch/sm42161162 Sun, Yat-sen(1897) Kidnapped… Continue reading 国王陛下戴冠記念第二回イングランド史動画投稿祭参加作品参考文献リンク集
Untitled
重い本が読めなかったので、軽い本をご紹介します。 フランスの文豪、バルザックによる「役人の生理学」。なお、私は文学好きではないので、バルザック作品など初めて読んでいます。なぜ読んだか?行財政史が好きだからですかね… 本書が書かれたのはバルザックにとっては晩年に差し掛かる1841年、7月王政期のフランスでした。当時のフランスといえば産業革命の時代ともいえます。王政といえども、1830年憲法下の立憲君主制であり、貴族制や世襲制が廃止され、直接税200フラン以上の制限選挙(有権者は全人口の1%に満たない)が実施されており、当時としては民主的な社会が始まっていました。そんな社会の縁の下の力持ちが大量の事務を公正に実施する役人たちです。住民登録、都市計画、公金の管理、公共事業の実施。どれをとっても民営化などしたら公共サービスが平等に国民にされず、誰もが平等なはずである民主的な社会の基盤が揺らぎます。今なお私たちを支える黒子たちですが、まぁ、評判が悪いところでは悪いものです。税金泥棒、仕事が遅くて融通が効かない、どうでもよさそうな細かいところばかり気にする、挙げ句の果てにはそう言った仕事のやり方をお役所仕事などと…。そんな悪評は今に始まったことではありません。バルザックの時代も同じ。いえ、むしろバルザックの時代ぐらいに始まったそうです。 以前の時代、第一帝政時代ですが、その当時のことをバルザックは皮肉を込めて懐古的に語ります。 「役人ほど素敵な商売はないといわれた時代があったことを知ってはいる。」 バルザックによれば、当時の役人は最高級の社交界にも出られたし、メチャメチャモテたそうです。というのも皇后など君主の一族が贔屓にしていた役人たちがいたからだそうで、役人の公共性というものがまだ確立していなかったからなのです。それが7月王制の立憲君主制により、信賞必罰をわきまえた君主から、忘恩の大衆に仕えることになり、閑職は攻撃対象となり、その栄華は終わりを迎えたのでした。 7月王政下で役人は事務室に拘束され、自由に立ち去る権利はなく、出世していないものは良いとは言えない賃金で働き続けました。バルザックがとりわけ注目したのはパリの中央官庁に勤める役人でした。今と変わらないじゃないかと思うものがある一方で、細かいところを見ていくと、現代(日本)との違いが浮き出てきます。19世紀のパリにはパソコンはおろか転写機もありません。謄本係という、今ならプリンターで十分代用可能な役職がありました。電子化されたデータもないので、今なら職員の誰かがちょっと兼任すれば済む文書管理責任者が整理係として独立した集団に。縁故採用が根強く、強力な後ろ盾があれば出世できるが、そうでなければ相当な忍耐力や適応能力が必要、などなど。 また、現代日本では見られない雇用形態も興味深いものです。それが試補→書記→課長補佐と続くもので、フランスでは1940年代まで続きました。試補(原文ではsurnumeraire、定員外の職員と言った意味のようです)とは正式な役人ではなく無給の見習いで、実家が太くない者は大変苦労したようです。戦前日本にも同名のもの(翻訳の都合でしょうが)があった制度で、明治20年勅令第37号において定められた「文官試験試補及見習規則」にあります。公立大学か試補試験合格者が役人になると最初に通る道でした。フランスにおいての採用基準の細かいところはバルザックは書いていません。もとよりこの本は役人の実態を詳細に記録するものではなく「こういう奴いるよな」と共感を誘い、一時の娯楽にするためのものなのですから。 そしてこのエッセーの真髄は、行動様式ごとに分けた役人分類で、ごますりだとか蒐集家(オタク)だとか商人だとかに分けています。スプラトゥーンのオオモノシャケみたいで面白いです。この中には大っぴらに副業が許されていた当時の役人事情を反映しているものもあります。その副業の程度は人により様々で、劇作家や小説家(三島由紀夫は大蔵省出身でしたね)、会社役員、演奏家、妻側の内職や店舗経営などなど。当時の役人生活はその薄給から副業せざるを得ず、バルザックはそのことで、国家が役人から俸給を奪い、役人が国家から時間を盗むと嘆いています。または、ロスチャイルド銀行の職員の待遇と比較し、あまりにも無駄があると。講談社学術文庫版では付録がついており、その中の『役人』というエッセイではフランス政府に対する改革案が載せられ、役人にはしっかり給料を支払い、人数を減らしてしっかり働かせるべきだと論じています。 バルザックの視点を離れ、山川出版社の世界歴史体系を見れば、高官は貴族やブルジョワに切望されたポストで、高い俸給にありつけば大ブルジョワ並みの生活となったそうです。昇進や指名の基準はあいまいなため、縁故採用、官職売買の慣行も続いたようです。そして積もり積もった不満はやがて1846年の凶作に端を発した不況、高学歴ワーキングプア、有望な王位継承者の不足から二月革命を招いたそうですが、それは本書の原書の最初の出版の後の話です。
国王陛下戴冠記念第二回イングランド史動画投稿祭
臨時ニュースにつき、当初予定しておりましたバルザックのエッセーの読書感想文に代えてお送りします。 ニュースとはニコニコ公式の生放送が私の謎企画を取り上げてくださるらしい(4月18日午後7時から)、ということです。 私の謎企画の経緯からまずは順を追って説明しましょう。 基本的にニコニコ動画で活動していた私ですが、昨年は何をトチ狂ったのか 中世イングランド史動画投稿祭 なる謎の企画をぶち上げておりました。なんか面白そうだから、というふわっとした動機によるものです。 告知動画はこちら 参考文献の提示を求めたりと、そこそこ厳しい参加条件を課していました。最悪自分一人が動画を揚げて「参加者は誰一人来ませんでした」と結果動画を出す覚悟でおりましたが、幸いにも多く参加者に多くの動画がそろい、それなりのお祭りになったのではないかと思っております。 これで一応の成功を収めたのをいいことに、今年も開催することにしたんですね 国王陛下戴冠記念第二回イングランド史動画投稿祭 を。去年と同じ時期にと思ったらなんと国王陛下の戴冠式の時期と被ってしまったのです。こうなればもう乗っかっとけと愛国心を商魂と結合させました。 また、去年は中世に限定していて、古代ローマやヴィクトリア朝が主力の投稿者仲間には少し不自由をさせてしまったことを反省し、投稿可能な範囲を広げており、少しテコの入れ方が変わりました。 こうして少しは練った参加要件を動画にしてアップロードし、あとは自分が期間内に動画をあげてほかの人の動画を見て、結果発表動画を作るのみ、そう思ってました。まぁ宣伝はそんなにしなくてもええやろと構えていたら、なんととんでもないところから宣伝してく出さる旨の申し出が…(もちろんユーザー企画を毎月まとめて動画で宣伝してくださっている方のことも忘れてはおりませんが) ある日(4月17日)職場から帰り、ベトナム製即席麺にお湯を注いで待っている間、某SNSを何気なく開くといつものごとく数件の通知。その中になぜかニコニコ公式によるものがあり、私の企画のことで相談があるからフォローしてDM送れるようにせよとお達しがありました。なにかまずいことでもしただろうか、どこかの団体が権利侵害で訴えてきたのだろうか、と悪い想像がよぎります。 しかし実際は、ニコニコ動画の公式生放送で宣伝してもいいかという承諾を求めるものでした。私はもちろん即承諾し、ついに公式に認知されたのかと恐れ多くなりました(中世イングランド史動画投稿祭の時点でニコニコトップページにユーザー企画ピックアップとして載ってはいましたが)。イングランド史の深い沼への入り口は、広ければ広いほど良いものです。このブログをお読みの皆様、ぜひ公式生放送を見て、イングランド史の動画を出してみませんか? 公式生放送の場所 第二回イングランド史動画投稿祭告知動画の場所
『オックスフォードブリテン諸島の歴史1 ローマ帝国時代のブリテン島』読書メモ
今回のブログも読書メモです。 前回は世界史リブレットと言う軽い本でしたので、今回はオックスフォード(慶應義塾大学出版会の翻訳版)からヘビー級の『オックスフォードブリテン諸島の歴史1 ローマ帝国時代のブリテン島』です。 本書のシリーズは今までイングランド史が中心になりがちだったUK周辺の歴史を、非イングランド地域での近年の国民意識の高まりを受け、その他の地域もまとめて「ブリテン諸島」として地理的区分としてとらえなおすという、欲張りな試みをしています。とはいっても一人の筆者や編者が体系的に通史を組み立てて書くことは難しかったようで、各分野の専門家による論文集に近い体裁です。 シリーズ内において本書はローマ時代を扱います。この時代について編者ピーター・サルウェイ氏は序論で、研究者には大きく二種類の態度があるとしています。一つはローマ帝国の一辺境に過ぎず、その歴史を叙述するには絶えず帝国の中心の動きを見据え続ける必要があるというもの。もう一つはローマの支配は表面的なものに過ぎず、真の意味でのローマ化はなく、独自の地域であったというものです。地域主義が盛んな昨今において、後者の方が受け入れられやすいのは容易に想像できましょう。編者は客観的な視点を重視するべきとしていますが、ローマンブリテン研究では特に公平性が保たれていないと考えています。そうした古くからの研究者の態度に警鐘を鳴らしつつ、本書の序論は終わります。 さて各章を見てみましょう。本書を通じて意識されていることはブリテン島が当時どれほどローマ的であったかと言うことです。ローマによって文字がもたらされたブリテン諸島。文献史学をやるならローマから見るしかないのです。それ以外のことが知りたければ考古学をやりましょう。実際イギリスの文化財保護政策や新しい調査手法によってローマン・ブリテンには新たなメスが通ずるっ込まれているのです。考古学による成果を交えつつ本書は新しいローマン・ブリテンの叙述を目指しています。 第1章「ブリテン諸島の変容 カエサルの遠征からボウディッカの反乱まで」 本章を担当したティモシ―・ウィリアム・ポター氏は古代ローマ専門の考古学者にして大英博物館の先史・ローマ時代ブリテン島部門の学芸員でした。そして2000年に55歳の若さで亡くなっています。本章では限られた資料の中でローマ時代初期のブリテン島の様相を叙述しています。本章でとりわけ注目されるのが、カエサルによる占領失敗からクラウディウスによる南部ブリテン島の占領までの期間に、すでに社会変化が始まっていたということです。社会変化の内容として挙げられるのは記録される部族名の違いなどから考えられるブリトン人社会における混乱(戦乱)、発掘により発見された品々から推測されるローマ文化の受容です。そしてカエサルによる占領後もブリトン人社会では保守派と新ローマ派に分かれ、不安定な状況が続いていたと考えています。今っぽく言えば、治安が悪かったのが初期ローマ時代のブリテン島だということです。筆者はブリトン人の自主性を評価し、ブリトン人自らがローマ化に進んでいったと考えているように思えました。 第2章「新たな出発 ボウディッカの敗北から三世紀まで」 本章を担当したマイケル・フルフォード氏は後期鉄器時代の定住地考古学、ローマ時代の都市と農村の考古学が専門のレディング大学の先生です。本章は第1章の続きとして読むことのできるものです。治安の悪かったブリタニア属州もローマの急速な拡大が止まり、安定へと舵を切り始めた時代を説明しています。イングランドの数か所の都市では、ボウディッカの反乱により形成された焦土層が年代特定の鍵となることなど、日本とは違ったイギリスの考古学の面白い特徴を紹介してくれています。この時代に北辺では長城を建設していますが、長城建設そのものに莫大な資材や労力が必要なことを考慮すれば、長城の建設ができたこと自体、ブリタニア属州の安定と豊かさを示しているとみています。ブリタニア属州は兵士の貯蔵庫的な役目も果たし、余裕があるときはカレドニア(スコットランド)に攻め入り、そうでないときは他所に兵を引き抜いて防御に徹したことも興味深い内容です。しかし3世紀ともなるとローマ内部での騒乱に巻き込まれ、属州内の都市も防御を迫られたようです。本章ではローマ側の記述が多く、ブリテン島はローマの一部として語られ、ブリトン人の動きに関する記述は少ないです。 第3章「古代末期のブリテン島 四世紀以降」 本章を担当したP.J.ケイシー氏はローマ時代末期のブリタニアについての著作のあるダラム大学の人です。なんかネットで拾えるよさげな情報が少なかったです。本章では第2章の続きでもあり、どうもローマ衰退期のブリタニアでは豊かな生活が維持されていたらしいことが記述されています。ローマで四分統治などが始まったころ、属州でも地方分権が進んだ結果、ブリトン人エリートが政治に関わりやすくなり、結果としてローマがブリタニアから手を引いたときにブリトン人政権が安定することができたのではないかとしていますが、資料が少なすぎてよくわからないようです。ローマが撤退した結果文明を支えられる人種がいなくなって元の先史時代の生活に戻ったかのような書きぶりだった昔の歴史叙述には批判的なのは確かです。とはいってもゲルマン人侵入以後急速にローマ的制度が失われていったことは認めています。ブリトン人がローマに順応し、ローマの制度を活用できていたとするあたり、ブリトン人に対する高評価が見て取れます。まぁゲルマン人に飲み込まれたんですけどね。 第4章「属州ブリタンニアにおける文化と社会の関係」 本章を担当したジャネット・ハスキンソン氏はイギリス版放送大学、オープン大学で古典の講師をしています。そのため著書はローマの文化史のものが多く、もちろんローマン・ブリテンについても著書があります。古典の先生であっても考古学的な成果を無視することはありません。本章以降は通史から離れて各分野の専門家による解説となります。かつて歴史家によって失敗と言われていたローマン・ブリテンの美術については、なぜそのようになったのかを考察するべきであるとし、その悲劇の弁護を試みています。ブリトン人の文化の中にローマのものが入ってきたんだからただ単純にまねしたんじゃないんじゃないかと言うことです。でも作品だけじゃそれが何だって言うのかよくわからないし、解釈はいくらでもできてしまうというのが限界のようです。 第5章「景観への影響 農耕、定住地、産業、インフラ」 本章を担当したリチャード・ヒングリー氏とデイヴィッド・マイルズ氏はいずれも考古学者。ヒングリー氏は鉄器時代とローマ時代のブリテン島の考古学で特に景観に注目しています。マイルズ氏についてはイングリッシュ・ヘリテッジという、イングランドの文化財行政を担う場所で主任研究員をしているようですが、同姓同名の人が多く、ネットではあまり多くのことが分かりませんでした。景観とは人の手が加わった地理のようなものと言えるでしょう。かつて森林が生い茂っていたブリテン島は狩猟者が獣を集めるために木を切ったり、農地を広げたりすることでハゲはじめ、土壌流出を引き起こし、低地には土砂がたまって湿地のようになったという話などです。居住地でいえば、ローマ兵の駐屯地を中心にローマ的な地区があり、それが道路で結ばれてその間にも広がり、低地部はローマ的な景観を見せていたようです。しかし山間部などはローマ以前の様式を残し、環濠定住地を使い続けたようです。それでもそうした遺跡の中からローマの工芸品が出てくるので、ローマの影響から逃れられていたわけではないそうです。ローマがブリテン島を放棄したのちもローマの景観は残り続けたという話は第3章と共通し、5世紀末にはその景観は消え失せたとしています。 第6章「世界の縁 帝国最前線とその向こう側」 本章を担当したデイヴィッド・J・ブリーズ氏はローマ時代の辺境に関する考古学の専門家で、スコットランドでの調査も行っていたようです。調査の成果によりアントニヌスの長城が世界遺産に登録されています。本章はローマの領域から目を離し、特にカレドニア(スコットランド)を解説しています。しかし、非軍事的定住地の出土遺物は少なく、遺跡の分布調査や発掘もそれほど進んでいないという悲しい現実があるようです。はっきりしていることはスコットランド、特に北部ではローマ由来の出土遺物はかなり少ないということで、先住民の意図なのか交易がなかったのか、とにかくローマ側との交流が少なかっただろうという話です。 結論 編者ピーター・サルウェイ氏による結論では、私のように集中して全部理解して読み切ることのできなかった人のために本書を改めてまとめています。あ、こんなこと書いてたっけなぁ見落としたなぁなど思いながら読む場所ですね。 さてここまで偉そうに読書メモを書きましたが、私自身読書力が弱いので、鍛えるために書かせていただいております。この読書メモを見たうえで本書を読んで、全然違う、まったく読書の助けにならなかった、などご指摘があるかもしれません。そこについてはすべて私の浅学の責任であるためここであらかじめお詫びいたします。ひとまず最後まで読んでいただきありがとうございました。 以下メモを書かせていただいた書籍のアマゾンのページです↓ オックスフォード ブリテン諸島の歴史〈1〉ローマ帝国時代のブリテン島
チェコ旅行の備忘録
はい、皆様ここではお久しぶりです。 なんだか新型コロナに関する規制が徐々に緩和されそうな情勢ですが、やはりまだ海外旅行を自由に楽しめるようになるまでは時間がかかりそうなので、今回も自由に旅行ができたあの頃を懐かしみながらブログを書いていきたいと思います。 今回紹介していくのはチェコ旅行の様子です。 私の動画シリーズでももう何回も擦っていますが、何回も擦るのは今までに行った海外の中でもトップクラスに感動した国だからでもあります。なお記事内の写真は全て筆者撮影です。 1.旧市街広場 やはりチェコと言えば印象に強く残っているのはこの旧市街広場です。旅行時は確か1月初旬とかで、辺りにはクリスマスマーケットの装飾がまだ多く残っていました。 その様子は上から見た写真だと分かりやすいです。屋台でスナックを購入し小腹を満たしたのは良い思い出となっています。 2.プラハ城 プラハ城もまたチェコを代表する観光地でしょう。当時はあまり良いカメラを持っていなかったので(写真はi pod touchの第5世代で撮影)、画質はあまり良くないんですが、遠くに佇む幻想的な城の姿は強く印象に残っています。RPGだとラスボスが住んでそう。 実は… おそらく知る人はかなり少ないかと思いますが、私はチェコを含めた中欧の旅行動画を投稿してた時期があります。(現在は全て非公開) 当時はまだ○学生とか○校生でしたが、今思うと現在更新中の全世界解説につながるようなことをしてたんです。たまには初心を思い出すのもいいですね。 それではまた機会があればお会いしましょう、それでは~!
『宮廷文化と民衆文化』読書メモ
歴史を学ぶものは動画なんか見ずにちゃんとした本を読むべきなのは当然のことなのですが、私は動画を作るために本を読んでばかりで、いつの間にか本を読むことを目的とした読書ができなくなっておりました。 そこで今回からは今後の読書モチベーションのために本を紹介していくこととしました。しかし、読書がはかどっていなかった私に紹介できる本は今のところこの以下の本ぐらいでしょうか。 『宮廷文化と民衆文化』世界史リブレット …薄い本です。今度はごつい本を紹介するので許して… 本書はブルゴーニュからブルボンまでの宮廷文化とフランスの近世民衆文化を取り上げて、その二者がブルジョワ階級の勃興で統合されるところまでを扱っています。とはいっても内容はほぼ宮廷文化で、民衆文化とブルジョワの説明はわずかです。私は民衆文化やブルジョワ文化などより宮廷文化に興味があったので全く問題ありませんでしたが、民衆文化側に興味を持たれている方にはお勧めできないでしょう。ただし18世紀の生活に付随した文化を勉強し始めるためならいいのではないかと思います。 さて軽く各章の内容をお伝えしますと以下のようなものです。 ①ブルゴーニュとウルビーノの宮廷 本章で宮廷文化の始まりは15世紀ごろのブルゴーニュであると述べられています。それ以前の宮廷文化、シャルル・マーニュやアリエノール・ダキテーヌと分けたのは武だけではなく文の力を有して形成された文化だからだとしています。晩餐はもちろん、音楽や蔵書、入市式などの儀礼において当時西欧において最も壮麗なことでブルゴーニュは知られていたのです。そのブルゴーニュに次いで紹介されるのはルネサンス期のイタリア宮廷であり、特にウルビーノを中心にしています。宮廷は王の住居であるだけでなく、それまでの修道院や教会に代わる文化の発信地でもあることが様々な部分から語られています。 ②フランスの宮廷 宮廷と言えばだれもが思い浮かべるバロックからロココの時代のヴェルサイユ。ベルばらの聖地です。ブルゴーニュやウルビーノが栄えていたころのフランスは、内乱やらペストやらで悲惨な状況でした。それが収まっても宗教改革による動乱が起こり、七転八倒の時代が続きました。そうした状況の中でも着実にルイ14世時代に花開く宮廷文化の下地が出来上がっていることを示しています。特に下積み時代のフランスに特徴的な移動宮廷の記述は興味深いです。そのあとは皆さんご存知の、ヴェルサイユに固定された宮廷文化の王道です。国王の行動がすべて儀式と化す、24時間舞台の上のような生活。そして収入源を求める貴族たちの阿諛追従。そりゃプチ・トリアノンに農場を作ってのんびりもしたくなりますね。 ←プチ・トリアノンです。こっちはヴェルサイユ宮殿。たまに来る分には豪華でいいところですが、ここで暮らせとなれば話は別。 ③民衆文化 民衆文化は普段の自分の周りでも何か片鱗が見えてきそうな内容です。不安から逃れるようにお祭りの時には騒ぎ、情けない男は集団でつるし上げて制裁する。暴力性が垣間見える部分もありますが、なんだ人間ってそんなに変わってないんだなと思えます。庶民本の普及で本が非日常を与える役割を担い始めたと書かれているところは、あぁ古き良き時代が去っていくのだなと郷愁を感じずにはいられません。 ④ブルジョワ文化による統合 本章はわずか4ページです。放埓な財政が生み出した買官制度により宮廷にやってきたブルジョワが、宮廷外にその高度な文化を持ち出していくというところを説明しているのですが、それがどうやって民衆文化と融合して現代文化になったかまでは説明してはいません。そこからさきは読者が調べる課題なのかもしれません。 と以上のように後半は記述が少ないのですが、その直後に参考文献が列挙されています。初学者にやさしい世界史リブレット、とりあえず何から読んだらいいか悩んだときにぜひおすすめのシリーズです。
世界史小話~クローヴィスの改宗~
世界史教科書では、クローヴィスの改宗について 「正統派キリスト教のアタナシウス派に改宗」 ということだけが記されていて、改宗以前はどうだったのかが明らかではありませんでした。中には 「改宗」という語に引きずられて、 「アリウス派からアタナシウス派キリスト教に改宗」 などと補っているものもありますが、これは明白な誤りです。誤解の余地のないように 「異教から」 という語を入れて説明しなくてはなりません このことについての出典は何かというますと、従来の諸研究と同様、教科書でもトゥールの司教グレゴリウス (五三八~五九四年頃)が著した 『歴史十書』 (フランク史) に依拠しています。 『歴史十書』 は、史料の乏しいメロヴィング朝フランク王国史にあって唯一と言ってもよい最重要の叙述史料です。「クローヴィスの改宗」 については、 『歴史十書』 の 「第二書」 に記されています。それの内容は、異教の神々の偶像を信奉していたクローヴィスは、ブルグンドの王族出身の王妃クロティルデが信じるキリスト教 (アタナシウス派) を、彼女がしきりに勧めるにもかかわらず、拒否し続けていた。ところがあるときアラマン人との戦いで劣勢に立たされ全滅に瀕した際、クローヴィスは異教の神々ではなく、イエス=キリストに祈って勝利を得た。これによりクローヴィスは、クロティルデが招いたランスの司教レミギウスの手で部下三千人以上とともに洗礼を受けた、というものです 「部下三千人」 との記述が、 『新約聖書』 の 『使途行伝』 二章四十一節にあるペテロが三千人を改宗させた話を下敷きにしているなど、グレゴリウスの叙述には護教的な脚色が多く、戦いの最中にクローヴィスがイエス=キリストに祈ったかどうかも含めて、すべてを事実とするわけにはいかないでしょう。しかし、教科書本文にも記したように、クローヴィスがこの改宗によって、ガリア各地でキリスト教の司教として地域社会を支配していたローマ人貴族層の支持を取りつけ、そのことによってガリアの支配を確実なものにしたことは間違いありません。 参考文献 トゥールのグレゴリウス著・兼岩正夫ほか訳注 『歴史十巻 (フランク史) 』 Ⅰ・Ⅱ 東海大学出版会一九七五~七七年