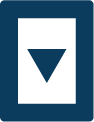歴史を学ぶものは動画なんか見ずにちゃんとした本を読むべきなのは当然のことなのですが、私は動画を作るために本を読んでばかりで、いつの間にか本を読むことを目的とした読書ができなくなっておりました。 そこで今回からは今後の読書モチベーションのために本を紹介していくこととしました。しかし、読書がはかどっていなかった私に紹介できる本は今のところこの以下の本ぐらいでしょうか。 『宮廷文化と民衆文化』世界史リブレット …薄い本です。今度はごつい本を紹介するので許して… 本書はブルゴーニュからブルボンまでの宮廷文化とフランスの近世民衆文化を取り上げて、その二者がブルジョワ階級の勃興で統合されるところまでを扱っています。とはいっても内容はほぼ宮廷文化で、民衆文化とブルジョワの説明はわずかです。私は民衆文化やブルジョワ文化などより宮廷文化に興味があったので全く問題ありませんでしたが、民衆文化側に興味を持たれている方にはお勧めできないでしょう。ただし18世紀の生活に付随した文化を勉強し始めるためならいいのではないかと思います。 さて軽く各章の内容をお伝えしますと以下のようなものです。 ①ブルゴーニュとウルビーノの宮廷 本章で宮廷文化の始まりは15世紀ごろのブルゴーニュであると述べられています。それ以前の宮廷文化、シャルル・マーニュやアリエノール・ダキテーヌと分けたのは武だけではなく文の力を有して形成された文化だからだとしています。晩餐はもちろん、音楽や蔵書、入市式などの儀礼において当時西欧において最も壮麗なことでブルゴーニュは知られていたのです。そのブルゴーニュに次いで紹介されるのはルネサンス期のイタリア宮廷であり、特にウルビーノを中心にしています。宮廷は王の住居であるだけでなく、それまでの修道院や教会に代わる文化の発信地でもあることが様々な部分から語られています。 ②フランスの宮廷 宮廷と言えばだれもが思い浮かべるバロックからロココの時代のヴェルサイユ。ベルばらの聖地です。ブルゴーニュやウルビーノが栄えていたころのフランスは、内乱やらペストやらで悲惨な状況でした。それが収まっても宗教改革による動乱が起こり、七転八倒の時代が続きました。そうした状況の中でも着実にルイ14世時代に花開く宮廷文化の下地が出来上がっていることを示しています。特に下積み時代のフランスに特徴的な移動宮廷の記述は興味深いです。そのあとは皆さんご存知の、ヴェルサイユに固定された宮廷文化の王道です。国王の行動がすべて儀式と化す、24時間舞台の上のような生活。そして収入源を求める貴族たちの阿諛追従。そりゃプチ・トリアノンに農場を作ってのんびりもしたくなりますね。 ←プチ・トリアノンです。こっちはヴェルサイユ宮殿。たまに来る分には豪華でいいところですが、ここで暮らせとなれば話は別。 ③民衆文化 民衆文化は普段の自分の周りでも何か片鱗が見えてきそうな内容です。不安から逃れるようにお祭りの時には騒ぎ、情けない男は集団でつるし上げて制裁する。暴力性が垣間見える部分もありますが、なんだ人間ってそんなに変わってないんだなと思えます。庶民本の普及で本が非日常を与える役割を担い始めたと書かれているところは、あぁ古き良き時代が去っていくのだなと郷愁を感じずにはいられません。 ④ブルジョワ文化による統合 本章はわずか4ページです。放埓な財政が生み出した買官制度により宮廷にやってきたブルジョワが、宮廷外にその高度な文化を持ち出していくというところを説明しているのですが、それがどうやって民衆文化と融合して現代文化になったかまでは説明してはいません。そこからさきは読者が調べる課題なのかもしれません。 と以上のように後半は記述が少ないのですが、その直後に参考文献が列挙されています。初学者にやさしい世界史リブレット、とりあえず何から読んだらいいか悩んだときにぜひおすすめのシリーズです。
Category: 地域
戦時中の鉄筋コンクリートについて、お話します。
まず、鉄筋コンクリートとはなんぞや。 明けましておめでとうございます。2023年もよろしくお願いしたりしなかったりしますね。 そんな新年の挨拶もほどほどに、今回の主題である鉄筋コンクリートについてますは話しておきましょうか。 鉄筋コンクリートとは、コンクリートの芯に鉄筋を配することで強度を高めたものを指し、コンクリートは圧縮力に強い反面、引張力には弱く、一度破壊されると強度を失う一方鉄はその逆で、引張強度が高い反面、圧縮によって座屈しやすいが、容易には破断しない粘り強さ(靱性)を持つを両者を組み合わせることで互いの長所・短所を補い合い、強度や耐久性を向上させるものが鉄筋コンクリートであります。 これは現代の鉄筋コンクリート 戦時中の鉄事情 さて、そんな鉄筋コンクリート君ですが、戦時中はどうだったのでしょうか? 戦時中で鉄と言えば、ある程度ミリタリーや近代史を齧っている皆様でしたら、昭和16年に公布された金属類回収令による金属供出によって寺の鐘やら学校や公園やらの銅像が撤去されて溶かされて資源化、軍事転用されたというのは良く知っている事でしょう。 何を隠そう、戦前の日本は鉄鋼産業に問題を抱えていた国でした。 まぁ、仮想敵国である米帝から屑鉄を輸入していた時点である程度は察してください。 鉄鋼産業は、鉄鉱石を製錬して鉄を作る「製鉄」と、鉄鋼製品の元である銑鉄を加工して鋼鉄や特殊鋼を作る「製鋼」に分けられます。 そして、鉄鉱石を製鉄して鉄にするよりも、屑鉄を溶かして鉄にするほうが、ずっと安く鉄を作れます。 戦前の日本は、後者の製鋼はそれなりの水準でしたが、前者の製鉄はイマイチでした。 で、屑鉄を買ってくれば「製鉄」する必要が無かったので、日本は屑鉄需要がとても高かったのです。 実際、日本は鉄鋼は80%程度を自給していましたが、その元となる銑鉄の自給率は60%に届きません。 さらに、日本の製鉄産業は経営が苦しくて技術革新が進まず、その製品である銑鉄の品質もイマイチでした。 そんな中で、船、自動車、鉄道、建築材などで大量のスクラップを出し、比較的品質の良い屑鉄をたくさん出すアメリカからは禁輸、果てには戦争までしようというのです。頭を抱えたくなりますよね。 鉄不足の中での鉄筋コンクリート建築 なので戦時中の日本は鉄不足に悩まされました。それは戦時中に建てられた鉄筋コンクリート建築にも見るとこができます。 例えば、「戦争」で「コンクリートの塊」と言えばまず頭に浮かぶと思われるのが、トーチカ、特火点とか言われる奴ですね。 私は昔、北海道に住んでいたのですが、北海道はその土地の広大さからか、あまり戦争遺構が撤去されずに放置されているパターンが多く見られます。そのため、苫小牧や網走といった米軍の上陸が予想された海岸線には未だにトーチカが多く残っています。 北海道に今も残るトーチカ跡。こういうのが多いのが北海道のいい所である。 その中でも私は厚真町の海岸線にあるトーチカを5年ほど前に見に行き、天井に登ったりしたのですが、崩れた壁面からは一本も鉄骨が出ていない。 少し離れたところにあったトーチカの基礎らしき場所も鉄骨が30センチ間隔で1本ずつ出ているといった状況。完全に鉄不足から鉄筋をケチったり使用しないでこれらを乱造していたという切羽詰まった当時の状況がこういったところからも見て取ることができます。 これだと鉄筋の引張力と粘り強さの恩恵を受けられない訳ですから、強度の落ちたトーチカで米軍の砲爆撃に耐えられるのかとても心配です。 また、去年の夏に南相馬市に行った時……と言っても本来の目的は相馬野馬追と南相馬市博物館に静態保存されているC50形蒸気機関車を見に行くのが目的だったのですけれど。 南相馬市博物館に静態保存されているC50。大正の傑作8620形を再設計したものの、その優秀な点を再設計でほぼほぼ潰してしまった悲しい子である。 この103号機はC50の特徴の一つであった調子の悪い本省細管式給水温め器を取り外してあるようだ。 その南相馬市博物館には戦時中に製造されたコンクリート柱の断面があり、それには鉄筋の代わりに竹が骨組みとして使われていたのです。鉄筋ならぬ竹筋コンクリートです。竹のしなやかさを鉄筋の代用としようとしたのでしょうがそれでも強度は落ちているであろう事と、腐食に弱い事は想像に難くありません。 これが博物館内と、静態保存されているC50の隣に腰掛けとして置いてあるのです。 「こんな貴重なものを腰掛けにするだなんて……なんて贅沢なことをしているんだ」と思いながら腰掛けてきました。 いい歴史成分の摂取になりました。 C50の隣に腰掛けとして設置されている竹筋コンクリート。環状に空いた穴の部分に竹が通っている。 鉄道レールと鉄筋コンクリート建築 さて、交通面では同じく昭和16に、不要不急線と指定された鉄道は線路がはがされ、レール等の金属が軍事転用されました(札沼線や白棚線など) 鉄道レールは不要不急線から引っぺがされた後は、もちろん溶かされたものもあったでしょうが、レールは入ってしまえばまっすぐな棒。なので鉄筋コンクリートの鉄筋として建材に流用されたものもありました。 例えば、厚真町にある共和トーチカでは崩れたコンクリート壁面からレールが見えるところがあり、レールをそのまま建材として流用したのが分かります。 このように戦時中の日本は深刻な鉄不足に悩まされながら、あるものを節約したり流用したりして、今の建築基準ではお粗末と言わざるをえない鉄筋コンクリート建築をして祖国防衛をしようと奮闘していたのです。
歴史好きだった私が、中国文学・思想を専攻に選んだワケ
模擬授業「道教はいつ成立したか?」 さて、共通テストもまもなくという時候となりました。 (いちおう当チャンネル視聴者の1~2割はこれから大学、という世代です) そうした若い「歴史好き」のみなさんの参考に、私の進路選びのことを述べたいと思います。 「世界史」をうたっているチャンネルですが、私は中国学(文学・思想哲学)を専攻としています。 (「中国史」は「中国学」含まれることもありますが、ここでは別個とします) 1月7日に挙げた動画も、 中国思想及び、その隣接分野である日本思想・仏教・神道を取り上げたものです。 しかし、中高生の頃の私は「歴史好き」であり、史学を専攻するつもりだったのです。 オープンキャンパスの思い出 「中国学の方がいいかも」と思ったキッカケは 高校二年時のオープンキャンパスで受けた「道教はいつ成立したか?」というテーマの模擬授業でした。 (以下、記憶だけでなく、現時点の学問的知識に基づきます) 先生が受講者に問いかけ、私を含む3名が回答します。 ①私は「老子」②ある者は「後漢」 ③またある者は「3~4世紀」 先生はどれも「正解」とおっしゃいました。 ①老子 道家(老荘)思想は黄帝・老子を開祖と称して、漢代には「黄老」とよく併記されます。 (黄帝はもちろん、老子も実在があやしいですが) そして道教においてこの両者は開祖のような位置づけとなっています。 道教側の主張として「道教が老子にはじまる」から、私の「老子」という回答を正解としてくださいました。 しかし、歴史的にいえばこれは事実とは異なります。 道家思想も道教もどちらも「Taoism(タオイズム)」ですが、道教は道家思想とは区別します。 ②後漢 道教は道家の延長線上にあるのは間違いなく、老子及び書物『老子』を重んじますが、 不老不死を目指す神仙説や陰陽五行に道家思想が混ざって宗教性・神秘主義色が濃くなっています。 そのために道家の哲学とははっきり区別されます。 厳密な正解とは「②後漢」です。最初の道教教団といえるのは、『三国志演義』でもおなじみの太平道と五斗米道です。 ③3~4世紀 しかし、同じく後漢に中国に伝来した仏教、「国教」として地位を確立した儒教とくらべると稚拙な存在でした。 仏教教団を参考に教団組織をつくり、これらと「三教」として肩を並べさせたのは、北魏の寇謙之です。よって先生は「③3~4世紀」も正解とされました。 (「確立」だったら寇謙之で間違いないですね) この模擬授業は、複数の大学で聞いた歴史学よりも遙かに面白く感じました。 いざ受験という時、史学科も受けましたが、中国文学とか、東洋哲学とかいうような名前の学科も受け、 結果、中国学の道を歩んでいくこととなりました。 難しい学科選び 「中国史好き」の方には『史記』ファン、「三国志」ファンが結構いると思いますが、 歴史学よりも中国文学を専攻にした方が幸せだったろうなという人をたまに見かけます。(その逆もしかり) 「史学」「文学」「哲学」は隣接領域であり、ある程度はどうにかなりますが 最初に学ぶのは、その分野の概説です。「イメージしてたもの、やりたかったことと違う」ということはめずらしくありません。 (文学研究者が歴史について書いたり、歴史学者が思想について語ったりなんてよくあるので、本当にどうにかなるのですが、最初に興味持てないと続けるのは難しい思います) 選ぶ前に本を読もう! 今年受験生、これからが正念場ですね。見事複数の学科に合格されたとして、「そのまま第一志望を選ぶ」前にちょっと待った! 学問領域が異なるなら、決める前にその学問に関係する新書本を数冊読んでみてください。 「イメージと違った」「こっちの学科の方が面白そうだ」ということが十分あり得ます。 来年以後受験生という方も、オープンキャンパスの模擬授業もいいですが、ついで担当教員にお勧め本を聞いてみてください。 転学・転学の制度もありますが、面倒ですからね。
『花神』はいいぞ。(おすすめ大河ドラマ紹介 第2回)
※今回は、とある大河ドラマ紹介文です。 ネタバレ注意! こんにちは、いのっちです! 年末の忙しい時期にも関わらず、私のブログを読みに来てくださって本当にありがとうございます! 「世界史べーた(仮)」開設からもうすぐ1年が経ちます。 先日はVtuber様との出張コラボ生放送が実現するなど、活動の幅が益々広がってきて非常に嬉しい限りです♪ 今日は私が歴史好きになった理由の一つ「大河ドラマ」の御紹介をさせて頂きたいと思います(季節感なし!)。 今回御紹介させて頂くのは、幕末の長州を描いた作品『花神』(1977年[昭和52]放送)を御紹介します! (例によってリアルタイムで視聴していたわけではなく、総集編を観たことがあるだけですが💦) 本作は司馬遼太郎さんの小説『花神』を中心に、『世に住む日々』『十一番目の志士』『峠』などの小説を組み合わせた物語が原作になった作品です。 主人公は原作と同じく日本近代軍制の創始者である「大村益次郎(村田蔵六)(演:中村梅之助さん)」です。ただし、本作は長州藩を中心とする群像劇なので、「吉田松陰(演:篠田三郎さん)」や「高杉晋作(演:中村雅俊さん)」など松下村塾周辺の人々についても大きく取り上げています。 ドラマの中でも、変革の時代は三種類の人間によって成されると紹介されていました(思想家:吉田松陰、戦略家:高杉晋作、技術者:村田蔵六[大村益次郎])。 因みにタイトルの「花神」ですが、「花咲か爺さん」という意味だそうです。幕末という短くも激動の時代に命を燃やして一花咲かせた人々を描いた本作に相応しいタイトルだと思います♪ 長州の村医者出身の村田蔵六が蘭学修行の為、大阪にある緒方洪庵の「適塾」(同窓には福沢諭吉・橋本左内などがいる)の門を叩くところから本作は始まります。 好学家で優秀だった蔵六ですが、特段野心があるというわけではなかったので、平穏な時代であれば故郷の町医者として一生を終えていたはずでした。しかし時代がそれを許しません。蔵六は技術者、そして軍人として故郷長州の動乱に巻き込まれていきます。 あと開明的で合理的な学者肌の印象が強い蔵六ですが、本作では少し違う一面を垣間見ることが出来るシーンもあります。 恩師・緒方洪庵の弔問の席において、蔵六は福沢諭吉に「なんで(蘭学を学んだあんたが、無謀な攘夷を主導している)長州なんかにいるんだ?」と問われす。 それに対して蔵六は憤然として答えます。 「攘夷の何が悪い!福沢のように物分かりのいい奴ばかりでは日本は滅びる。確かに俺たちは蘭学を学んだがそれがどうした。小さい国の癖に横柄な面をしている奴を討ち払うのは当たり前だ!(要約)」 ただの冷静な合理主義者ではない村田蔵六の熱い内面がほとばしる名シーンだと思います。(実際に『福翁列伝』に似たようなエピソードがあるとか) 他にも魅力的な人物はたくさん登場しますが、個人的なお気に入りはやっぱり「高杉晋作」ですね。 どこまでが史実なのかは存じ上げませんが、本作では高杉の破天荒エピソードがこれでもかというくらい採用されています。 例えば… ・将軍の行列にやじを飛ばす。 ・突然出家する。 ・講和会議の席で古事記を暗唱して相手の要求を有耶無耶にする。 などなど(これでもごく一部です) しかし、「強質清識凡倫に卓越す(吉田松陰)」「動けば雷電の如く発すれば風雨の如し(伊藤博文)」と称された高杉晋作。 勿論ただの問題児というわけではなく、「維新回天の原動力」として要所要所で大活躍していきます! 個人的に一番好きなエピソードでは「功山寺挙兵」ですね。 京都での戦い(禁門の変)に敗れたうえに、列強の連合艦隊にも完膚なきまでに叩きのめされ、窮地に立たされた長州藩。藩の上層部は幕府への恭順を決定、隊の存続を優先する奇兵隊の同志たちもその方針に理解を示そうとします… Continue reading 『花神』はいいぞ。(おすすめ大河ドラマ紹介 第2回)
世界史小話~クローヴィスの改宗~
世界史教科書では、クローヴィスの改宗について 「正統派キリスト教のアタナシウス派に改宗」 ということだけが記されていて、改宗以前はどうだったのかが明らかではありませんでした。中には 「改宗」という語に引きずられて、 「アリウス派からアタナシウス派キリスト教に改宗」 などと補っているものもありますが、これは明白な誤りです。誤解の余地のないように 「異教から」 という語を入れて説明しなくてはなりません このことについての出典は何かというますと、従来の諸研究と同様、教科書でもトゥールの司教グレゴリウス (五三八~五九四年頃)が著した 『歴史十書』 (フランク史) に依拠しています。 『歴史十書』 は、史料の乏しいメロヴィング朝フランク王国史にあって唯一と言ってもよい最重要の叙述史料です。「クローヴィスの改宗」 については、 『歴史十書』 の 「第二書」 に記されています。それの内容は、異教の神々の偶像を信奉していたクローヴィスは、ブルグンドの王族出身の王妃クロティルデが信じるキリスト教 (アタナシウス派) を、彼女がしきりに勧めるにもかかわらず、拒否し続けていた。ところがあるときアラマン人との戦いで劣勢に立たされ全滅に瀕した際、クローヴィスは異教の神々ではなく、イエス=キリストに祈って勝利を得た。これによりクローヴィスは、クロティルデが招いたランスの司教レミギウスの手で部下三千人以上とともに洗礼を受けた、というものです 「部下三千人」 との記述が、 『新約聖書』 の 『使途行伝』 二章四十一節にあるペテロが三千人を改宗させた話を下敷きにしているなど、グレゴリウスの叙述には護教的な脚色が多く、戦いの最中にクローヴィスがイエス=キリストに祈ったかどうかも含めて、すべてを事実とするわけにはいかないでしょう。しかし、教科書本文にも記したように、クローヴィスがこの改宗によって、ガリア各地でキリスト教の司教として地域社会を支配していたローマ人貴族層の支持を取りつけ、そのことによってガリアの支配を確実なものにしたことは間違いありません。 参考文献 トゥールのグレゴリウス著・兼岩正夫ほか訳注 『歴史十巻 (フランク史) 』 Ⅰ・Ⅱ 東海大学出版会一九七五~七七年
2019年にロシア行ったって話
どうもゆはるです。 今回は私の旅行記第三弾として、2019年に行ったロシア旅行の様子をお伝えします。 言わずもがな、2022年11月現在、ロシアに観光旅行なんて考えることもできない状況です。 外務省が出してる危険情報ではロシア全土が「危険レベル3」でウクライナ国境付近は「危険レベル4」、ロシア政府が自国民含め出入国を著しく制限していますから、入国はできても出国できないなんて事態に陥るかもしれません。 ロシア、まぁそこそこに観光する場所がある国です、今回惜別の意も込めましてロシアの見どころをいくつか写真も合わせてお伝えしたいと思います。この記事に載っている写真は全て私ゆはるが撮影したものです。 赤の広場 やはりロシアといえば最初に思いつく観光地はここでしょう。正教会独特の建造物は一度見れば印象に残ります。 一応遠目で見た写真もあったのでペタり。2019年の赤の広場は自分以外にも観光客がたくさんいて平和でした。 また、写真はありませんが(写真撮影禁止のため)、赤の広場の近くにはレーニンの遺体を見ることができる施設がありました。レーニンの身長は165cmで、おそらく見物した人の多くは小柄だなという印象を持ったでしょう。ちなみにプーチン大統領の身長は168cm、スターリンの身長は163cm(両人共に諸説あり)で、ロシアの歴史的重要性を持つ人物は小柄な人が多いんですね。エリツィンは187cmだったけど。 エルミタージュ美術館 エルミタージュ美術館もロシアの観光名所として三本指に入るくらい有名ですね。 私は会えませんでしたが、展示物をネズミから守るため、エルミタージュ美術館では70匹もの猫を飼っているというのは有名な雑学です。 美術館では様々な展示が行われていましたが、一番印象に残っているのは2018年より展示が始まったというニコライ2世のワイシャツです。 そう、あの大津事件の時のやつです。 警察官の津田三蔵に右耳上部をサーベルで切りつけられたこの事件、その時に付いたと思われる血痕がワイシャツの首元部分にはっきりと残っていました。ちなみに写真撮影OKでした。 このワイシャツが展示されているという情報、なぜか日本語圏ではあまり知られていませんね。日本語で検索をかけてもロシア政府系メディアの「スプートニク」の日本語版の記事しか主にヒットしませんでした。 2022年にはロシアへの観光旅行が制限されたことを考えると、展示が開始された2018年からの4年間しか日本人が生で見る機会がなかったのかな? この写真実は貴重だったりして。 そんなわけでいかがだったでしょうか。 ロシア旅行はしばらく行けん、児島惟謙な情勢ですが、死ぬまでにはもう一度訪れてみたいとも思っています。西欧色の濃いサンクトペテルブルクと東欧色の濃いモスクワの対比とかね、楽しかったですよ。ロシア人も観光客の私には人懐っこくて親切でした。 ロシア旅行が気軽に行けるくらい平和な世界情勢に早く戻ることを願っています。それでは。
テューダー朝重要人物まとめ
現在ウルジーの動画を作っていますが、テューダー朝の重要人物について軽くまとめたいと思います(唐突)。 また若干書きかけの感もあるので、随時更新していきたいと思います。ひとまずヘンリー8世時代まで。 〇ヘンリー7世時代 ヘンリー7世の時代は薔薇戦争終結後の不安定な情勢を何とか押さえつけていた時代です。そのためにテューダー家の正当性をアピールしたり、有力者を財産罰で徹底的に締め上げ、王位僭称者は執念深く追い続けるなど、徹底的に対策を推し進めていました。この時代に蓄えられた王家の財産はヘンリー8世の活動を大いに支えました。 ①ヘンリー7世(1457-1509) テューダー朝の創始者。王家に近い血筋ですが、男系をたどるとウェールズ人であり、必ずしも血統がいいわけではありませんでした。ヨーク家のリチャード3世を倒して王位を得ましたが、リチャード3世は男系をたどると12世紀のイングランド王までたどれる由緒正しい王家の血筋のため、イメージ戦略で正統性をアピールせざるを得ませんでした。もちろんヘンリー7世を認めない勢力も多く、王位についてからも割れこそがイングランド王と名乗る人物にたびたび悩まされました。実務面では非常に有能な王で、帳簿を自身で管理したことで知られています。CV.石田彰が似合う王です。 ②エリザベス・オブ・ヨーク(1466-1503) ヘンリー7世が倒したヨーク家の王女です。ただし、叔父のリチャード3世とは対立していたウッドヴィル家の縁者であり、リチャード3世と戦う前から結婚の話がありました。即位後は王を支える王妃であり続けました。また、エリザベス・オブ・ヨークとの間に後継者を得ることは血統的に万全ではないテューダー家には欠かせないことでした。ヘンリー7世はエリザベスとの共同統治を避け、テューダー家の王家としての形式ために結婚式の前に戴冠式を行いましたが、臣民を安心させるにはやはり旧王家との連続が必要だったからです。生まれた後継者は二人で、一人がアーサー、もう一人がヘンリー8世でした。 ③アーサー・テューダー(1486-1503) ヘンリー7世待望の王子でした。幼少期から王にするために育てられ、外交のためスペイン王女との結婚もしましたが、そのあとすぐに流行り病でなくなりました。粟粒熱として知られる病気だったようで、発症したらほぼ死に至る病でした。ヘンリー8世にとっては兄にあたります。 ◯ヘンリー8世時代 言わずと知れたヘンリー8世の治世前半は敬虔なカトリック信者としてウルジーの力を借り、ヨーロッパ外交で存在感を示そうとしました。しかし、後継者不在を解消するために離婚をしようとしたところから宗教改革が始まりました。宗教改革では多くの人物がその渦に巻き込まれます。 ①ヘンリー8世(1491-1547) ヘンリー7世の第二の後継者でした。当初は王として育てる予定がなかったので、比較的自由に育てられましたが、兄アーサーの死で王となるための教育が行われました。兄に比べて開放的な性格で、陰湿だったヘンリー7世から王磯継承したころは歓迎されたようです。即位後はフランス領土奪還や存在感あるイングランド王国を目指しましたが、思うように成果は上がりませんでした。そうこうするうちに後継者ができないまま兄から引き継いだ王妃、キャサリン・オブ・アラゴンがアラフォーを迎え、後継者問題に直面すると子供を埋める若い王妃を求めます。そのための離婚の許可が国際情勢の問題で得ることができず、イングランドの宗教改革のきっかけとなる宗教改革議会を開きました。この過程で何人もの人物が処刑されたことは非常に有名です。しかし、ヘンリー8世にとっての宗教改革のゴールは教皇からの指図を受けない教会であれば十分だったので、教義面の改革についてはあまり問題になっていませんでした。離婚や処刑を繰り返して得られた男子の後継者はエドワード5世だけでした。 ②トマス・ウルジー(1475-1530) 治世前半のヘンリー8世を支えた枢機卿です。即位当初は政治に強い関心がなかった王のために実務の多くを担当していました。王国の本当の支配者はウルジーだと考えられていたほどでした。しかし離婚問題に直面すると、教皇庁の枢機卿としての立場と王国の大法官としての立場で板挟みになり、ヘンリー8世の意に沿った行動をとることができず失脚しました。あくまで教皇庁にイングランド教会が所属する形で離婚を成立させたかったからです。 ③キャサリン ・オブ・アラゴン(1847-1536) ヘンリー8世と最も長く連れそった王妃でした。スペインのカトリック両王の王女として生まれ、アーサー王子に嫁ぎました。アーサーが亡くなると、ヘンリー8世の即位までイングランドで人質のような生活をしましたが、ヘンリー8世の即位後は良き王妃としてその活動を支えました。問題は男子の後継者を残せなかったことで、そのことでイングランドの宗教改革を引き起こしました。キャサリン自身は敬虔なカトリックであり、ヘンリー8世に市場もあったので離婚を徹底的に拒みましたが、教皇庁とイングランドの教会を切り離す力技には勝てず、離婚となりました。 ④トマス・モア(1478-1535) イングランド随一の人文主義者で法律家でした。法律家や庶民院議員としても活動していましたが著作活動がよく知られています。ヘンリー8世の離婚問題については宣誓して認める予定だったが、思想家の性として、自身の心情と相いれない一文を宣誓書に発見したことで宣誓書にサインができず、処刑されることになりました。彼の死は映画にもなり、カトリックでは聖人として認定されています。 ⑤アン・ブーリン(1501-1536) ヘンリー8世の離婚問題の最大の元凶です。王妃キャサリン・オブ・アラゴンの侍女でしたが王の愛人となり、最後には王妃に上り詰めました。しかし健康な男子を生むことができず、近親相関等の罪の疑いで処刑されました。よく映画の題材になる人物です。 ⑥トマス・クロムウェル (1485-1540) ヘンリー8世の側近でした。王妃の離婚問題では主導的な役割を果たし、宗教改革を勧める原動力になった人物です。かつてはイングランドの行政が家産的なものから官僚的な物に移行するときに大きな役割を果たしたと考えられていましたが、この点には議論が多いです。王が3番目の王妃、ジェーン・シーモアを亡くすとアン・オブ・クレーヴスを手配しましたが、王はときめかず、婚姻は無効だったとしました。王の気に入らない女性を推薦したせいか、そのあとすぐ反逆罪で処刑されました。 ⑦ジェーン・シーモア(1508-1537) ヘンリー8世3番目の王妃でした。エドワード6世を儲け、ヘンリー8世待望の男子の後継者を産みましたが、そのすぐあとに産褥熱で死亡しました。 ⑧トマス・クランマー(1489-1556) ヘンリー8世の宗教改革を宗教面で支えたカンタベリー大司教でした。プロテスタントとして宗教改革を推し進めましたが、次代のメアリー1世の時代ではカトリックに反する人物だったので、処刑されました。 ◯エドワード6世時代 短い治世でしたが、プロテスタントとして宗教改革が本格化した時代でした。王は若くして亡くなったので、政治の実権は廷臣たちが握っていました。以下に挙げる人物はエドワード6世を除き、首と胴体が切り離された状態で死亡しています。 ①エドワード6世(1537-1553) ヘンリー8世待望の後継者として生まれました。マーク・トウェインの『王様と乞食』に登場する王様なのでご存知の方も多いでしょう(多分プリンセス・プリンシパルも一部元ネタは『王様と乞食』)。元来敬虔なクリスチャンのヘンリー8世の子供なので宗教教育をしっかりと受けましたが、政治的な背景でプロテスタントの教育を受けています。即位後はプロテスタント的政策を推し進め、廷臣たちも出世のためにプロテスタントに順応しました。しかし病弱だった上に、ヘンリー8世時代にスコットランド女王メアリーとの結婚の段取りに失敗したため、後継者を残さずわずか16歳で死去します。 ②メアリー・ステュアート(1542-1587) エドワード6世の結婚相手と目されたスコットランド女王です。スコットランド国内での結婚反対により、縁談は戦争に発展しました。元々父親のジェームズ5世はイングランドとの戦争の最中に死んだので、反発は無理もないことでしょう。なので対抗してフランス王と結婚しますが、すぐに死別し、スコットランド貴族と結婚します。ここまではあまりメアリーの特色は出ていませんが、国内での舵取りの下手さがこの後の悲劇につながりました。不倫問題を起こすし、国内で高まっていた宗教改革には背を向けてカトリックを突き通し、それでいてイングランドに亡命するのですから。さらにその亡命先でなぜかエリザベス1世の暗殺計画に加担して斬首されます。母方がテューダーの血筋なので、カトリック的論理から見れば私生児に過ぎないエリザベス1世を認められなかったというのでしょうが、あまりにも現実と折り合いをつけるのが下手な人物でした。 ③エドワード・シーモア(1500-1552) エドワード6世の母方の実家の人物なので当然のように護国卿の座についてプロテスタント政策を進めました。また、前述のメアリーとエドワード6世の結婚を成立させるために戦争を進めた張本人でもあります。しかし、急激な改革や、囲い込み等の社会変化に反発する反乱への対処が遅れ、ダドリーの台頭を許し、処刑されました。 ④ジョン ・ダドリー(1504-1553) ヘンリー7世時代に辣腕を振るったエドムンド・ダドリーの息子です。ヘンリー7世の財産罰による締め付けの実務を担っていたせいで父親はその王の死後にスケープゴートとして殺されました。幼少期に父親の権利が復活し、上流階級としての基盤が整うと、軍人として頭角を表していきました。その力でシーモアが鎮圧できなかった反乱を鎮圧し、護国卿の地位を得ます。しかし、どのような改革を進めるかなどに明確なビジョンを元々持っていたわけではなかったようで、シーモア以上のプロテスタント化政策を推進しました。彼にとって悲劇なのは、国王が夭折した結果、カトリックが復権することになり、シーモア以上に立場を崩されたことです。後述するジェーン・グレイを急遽対抗馬として女王にするも、メアリーに察知されて失敗し、首を切られました。 ⑤ジェーン・グレイ(1537-1554) ジョン・ダドリーの最後の足掻きの巻き添えになった可哀想な人。敬虔なプロテスタントで、少し遠いながらもテューダーの血筋を引いていたことが悲劇の始まり。元々の婚約者とは別れさせられ、女王に即位させられたと思ったらわずか9日で王座を追われ(トラスよりも短いのである)、命を助けてもらっても父親が反乱に加担してわずか16歳で首を切られました。何か悪いことをしたのでしょうか。なにもしていません。ただ血筋と時代のせいでした。
新規加入の敬仲です ~アイコンと加入目的について~
2022年秋から加入いたしました。中国屋の敬仲と申します。 アイコンとしている人物は梁啓超(1873 – 1929)。高校世界史においては、1898年の「戊戌変法」で師の康有為とともに登場します。 彼は思想家、ジャーナリスト、政治家、教育者、歴史家等々、多くの面を持っています。その中で一番の功績は、「近代化が必要だ」と当時の中国の人々に自覚させたことにあると考えます。 1895年に日本に敗れたことに端を発する変法運動から、1911年の辛亥革命にかけての16年間は激動の時代でした。政治・経済・外交の変化もさることながら、中国に欧米の思想・学問が堰を切ったように流入しました。 梁啓超は日本語でかかれた著作物を媒介として、欧米のあらゆる知識を得て、それを新聞雑誌の主筆として発信しました。同様のことは、孫文らの革命派もやっていました。政治的主張の発信では革命派が勝利したものの、知識の発信における影響力では梁啓超に及びません。 私が動画投稿を始めることを思い立ったとき、誰を手本にしたいか考えると、梁啓超をおいて他にありませんでした。 (アイコンに選んだ理由として、もちろん彼がイケメンだからというのもありますよ) 梁啓超の著書の翻訳には以下があります。 ・高嶋航 訳『新民説』平凡社東洋文庫 2014年 ・岡本隆司ら訳『梁啓超文集』岩波文庫 2020年 ※そのまえに 狹間 直樹『梁啓超:東アジア文明史の転換』岩波現代新書 2016年 を読もう! さて、実は私は歴史好きというよりも、古典好きというのが適切です。大学は中国古典を扱う専攻の出身です。(中国文学とか中国文化とか中国哲学とか東洋哲学とかのワードが名称に入っているところ) でも古典でとっつきにくいんですよね。中学・高校で地歴公民は得意だけど、国語の古文漢文はあんまり……って人も多いと思います。実際、言葉・文法がハードルですし、時代・ジャンルの偏りから、地歴・政経好きな人に魅力的なものは少なかったでしょう。 (古典に触れる大事なチャンス故に、勿体なく感じます。しかし他国や他ジャンルになると「国語」の枠から外れてしまうという問題もあります) この世界史べーた(仮)は「歴史を学ぶきっかけをつくる」「歴史の魅力を伝える」というのが主題ですが、ついでに古典も便乗させてもらおうと加入しました。 専門の中国ばかりになるとは思いますが、歴史理解の補助として積極的に古典を活用したり、古典の知識があってこその、思想史・宗教史等の動画を作っていけたらと思います。 (ブログの方もなんらかの形で中国に触れることになるでしょう)
栗田艦隊の反転について。お話しします。
~まえがき~ 以前、世界史べーたのマシュマロにこのような質問がありました。 戦後、米戦略爆撃調査団に対して「我々の主目的は機動部隊で湾内に入る目的は無かった」「(空母と輸送船が)両方いたら私は断然戦闘艦艇とわたりあったでしょう」という栗田中将の回答が全てを…続き→https://t.co/cJgagQuLrB#マシュマロを投げ合おう pic.twitter.com/FHUUeUHB3h — 世界史べーた(仮) (@sekaishibeta) July 31, 2022 これについてはツイートにもあるように、栗田長官は輸送船団と空母機動部隊を天秤にかけた結果。より価値のある空母を求めて艦隊を反転させたという訳です。 と言われても全然判断材料が足りないでしょうからそこらへんのお話をしていきましょう。 ~謎の反転。その真実~ 1944年10月25日0911時。サマール島近海。 第77.4任務群に属する「タフィ3」と称される護衛空母群との戦闘を終えた栗田艦隊旗艦大和は「逐次集レ」を命令。 大和からの命令を受けた各艦は終結を開始しますが、その中でも米軍機からの空襲は続いており。その規模は徐々に組織だったものになってきていました。 レイテに再度進撃を開始した栗田艦隊ですが、進撃中も空襲は続き、栗田長官の懐疑心は最高潮を迎えていた事でしょう。 なにせレイテ湾の敵情が全く分からないのです。 『サマール沖の戦闘中に目指す輸送船団は退避してしまったのではないか?』 『前日の0650時に最上艦載機の偵察情報であった戦艦4、巡洋艦2からなる戦艦部隊がレイテ湾で待ち構えているのでは?』 『空襲が組織的になってきたのは三群あると思われる敵空母機動部隊の残り二群が向かってきているのではないか?』 この時、小沢艦隊がハルゼー機動部隊を北方に誘引することに成功した報は栗田艦隊には届いておらず、サマール沖で撃破した空母部隊は正規空母の機動部隊の一群と考えられていました。 そして、ここで決定打となる入電が1100時に入ります。「ヤキ一カ」電です。 「0945スルアン灯台ノ5度113浬二敵機動部隊発見」 この南西方面艦隊からの情報に栗田艦隊司令部は大いに揺れました。 もととり「空船(輸送船)との心中は御免」という空気が艦隊首脳部に流れており、目指すレイテも昨日の最上機の情報以外、敵情が一切わからない中での機動部隊発見はまさに闇に差し込む唯一の光と言ってもいいでしょう。 例え戦死するなら艦隊決戦に死に場所を求めていた。栗田長官、小柳参謀長、大谷作戦参謀らによる協議の結果、艦隊は北方の敵艦隊に向かう事を決意し、未だに対空戦闘中だった1236時、栗田長官は「第一遊撃部隊ハ『レイテ』泊地突入ヲ止メ『サマール』東岸ヲ北上シ敵機動部隊ヲ求メ決戦爾後『サンベルナジノ』水道ヲ突破セントス」と打電。 ここに歴史は決したのであります。 ~もしも、栗田艦隊がレイテ湾突入をしていたら~ これはIFのお話です。と言ってもざっくりとしたのは以前にツイッタで話しましたが…… まぁ、あそこで栗田艦隊がターンしないでレイテ湾に突入しようにも、突入前に西村艦隊を打ちのめしたオルデンドルフ艦隊とぶつかるのは必死。 先のサマール沖海戦の結果も加味して日本艦隊が勝てたかというと……まぁ無理寄りでしょうなぁ https://t.co/X1XsCe6ZOt — 肉のZEKE22 (@zeke_22) July 31, 2022 それじゃあ、彼我の戦力差など夢物語では語れない、現実的な架空のお話をしていきましょうか。 さて、サマール沖海戦の後で栗田艦隊に残されていたのは 戦艦 大和、長門、金剛、榛名 重巡 羽黒、利根 軽巡 能代、矢矧 他、駆逐艦8隻といった陣容でした。 栗田艦隊には他にも重巡の鳥海、筑摩、鈴谷、熊野がいましたが、いずれもサマール沖海戦の米軍機による空襲や駆逐艦の雷撃により落伍または撃沈しており、鳥海には駆逐艦藤波、筑摩には野分が警戒艦として派遣されていました。(後に落伍艦、警戒艦は全て米軍の攻撃で撃沈している) その一方で、対峙するであろう米軍は半日前にスリガオ海峡で西村艦隊を撃破したジェス・B・オルデンドルフ少将の上陸支援艦隊が待ち構えており、TF78とTF79から成っており、その陣容は 戦艦 ミシシッピ、メリーランド、ウェストバージニア、ペンシルバニア、テネシー、カルフォルニア 重巡 ルイヴィル、ポートランド、ミネアポリス、シュロップシャー(豪海軍) 軽巡… Continue reading 栗田艦隊の反転について。お話しします。
紫電改part1 参考資料兼一部詳しく
紫電改part1参考資料兼一部詳しく 今回は紫電改解説動画part1の参考資料や動画ではマニアックすぎた内容の一部をご紹介します。 参考資料 ・碇義朗「最後の戦闘機 紫電改 起死回生に賭けた男たちの戦い」光人社 ・野原茂「海軍局地戦闘機」潮書房光人新社 ・海鳥の今までの取材内容一部 非公開の内容 紫電改の改造前機「紫電」では元になった十五試水戦(強風)から多くの変更点がありました。こちらは動画でご紹介しました、発動機、カウリング形状、側面形、垂直尾翼周辺など多くの変更点がありましたが動画で紹介していないものでは、「水銀式センサー自動空戦フラップ」、「操舵比変更装置」はさらに改良を重ねたものを搭載していました。 水銀式センサー自動空戦フラップ 水銀式センサー自動空戦フラップとは、フラップを空戦時に下ろし揚力を高め、旋回半径を小さくする、すなわち運動性能を向上させる空戦機動を”自動的に”最適の舵角をとれるようにしたものです。 作動のメカニズムは、発信機と称した、センサーの下部にある水銀槽の中の水銀が、ピトー管から入る静圧、動圧、および、旋回時の機体にかかる重力によって、上方に伸びる硝子筒の中を上下動します。 この上下動により硝子筒内の二つの電極に水銀が触れると電流が流れ、フラップが作動するメカニズムになっていました。 ちなみに、フラップの最大下げ角は30度となっており、零戦の60度に比べると半分ほどしかありません。 この自動空戦フラップに加え、川西技術陣が、操縦系統に採り入れたメカニズムがもう一つの技術「操舵比変更装置」です。 操舵比変更装置 通常、航空機は高速になるにつれ、各動翼の受ける風圧も強くなり、操作が重く、強い力が必要となります。速度が上がれば舵の動きが少しでもよく効くようになります。 逆に低速飛行時は、舵の受ける風圧が弱いと、操作が軽く、強い力を必要としなくなります。しかし、舵を大きく動かさなければ舵は効きません。 零戦の場合、各操縦索を通常よりあえて細めにし、剛性を低下、つまり伸びやすくし、一定の操縦感覚にしていました。 これを零戦より1tも重い紫電、紫電改で採用するのは不遇であったので、川西航空機は「操舵比変更装置」を作りました。 これは、操縦桿、および方向舵踏棒と昇降舵、方向舵操作索の間に、油圧で連動桿の固定位置を移動できる操舵比変更部を組み込み、フラップの動きに連動し、離着陸時(低速)、飛行時(高速)の二段階に切り替わるようにしたメカニズムです。 これにより、低速飛行時は操縦桿。方向舵踏棒を少し動かすだけで大きな舵角がとれ、高速飛行時はその逆になる、まさにパイロットにとって理想的な操舵感覚が得られました。 実はこれらの「自動空戦フラップ」、「操舵比変更装置」は当時の欧米各国に例がなく日本航空技術として十分誇れるものでした。すごいね 武装 強風 7.7mm機銃二梃 20mm機銃二梃 紫電、紫電改 20mm機銃四艇 上記のように20mm機銃四艇に武装が強化されていました。 まとめ 紫電改part2は紫電→紫電改まで行ければいいなって思ってます。頑張ります。 今週土曜日は神戸に撮影に出かけ「神戸戦跡巡り動画」を作ります。こちらはリアル映像なので私のチャンネル「海鳥のカフエラテ(カフェラテ)」で投稿します。こちらのチャンネルでは毎週土曜日21時から競馬予想配信してるので是非~ 紫電改part1もぜひご覧ください!








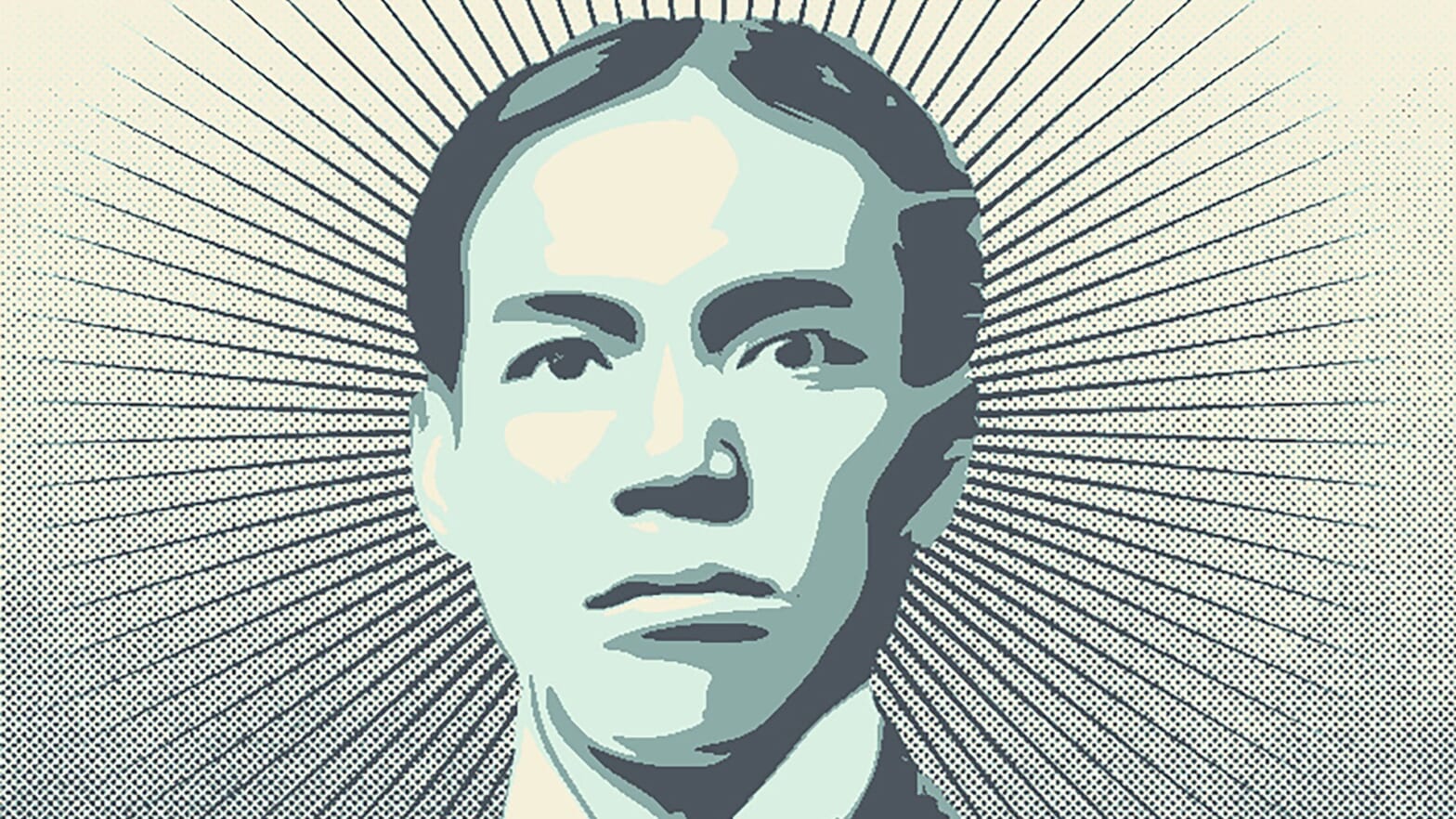

.png)